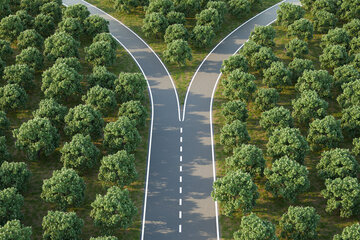日米協定による新たな投資モデル
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
増島 雄樹
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
バリュエーション&モデリング
小野田 峻

景気循環による経済的影響は企業にとって不可避なものです。しかし、世界および地域経済に対し長期的な見通しを持つことにより、企業は景気循環のリスクを最小化することができます。デロイトは、世界のビジネスリーダーたちに必要な、マクロ経済、トレンド、地政学的問題に関する明快な分析と考察を発信することにより企業のリスクマネジメントに貢献しています。
本連載では、デロイトのエコノミストチームが昨今の世界経済ニュースやトレンドについて解説します。今回は、Deloitte Insightsに連載中のWeekly Global Economic Updateの2025年9月15日週の記事より抜粋して日本語抄訳版としてお届けします。
目次

Ira Kalish
Deloitte Touche Tomatsu
チーフエコノミスト
経済問題とビジネス戦略に関するデロイトのリーダーの1人。グローバル経済をテーマに企業や貿易団体への講演も多数行っている。これまで47の国々を訪問したKalish氏の解説は、ウォール・ストリート・ジャーナル、エコノミスト、フィナンシャル・タイムズなどからも広く引用されている。ジョンズ・ホプキンス大学国際経済学博士号取得。
日米協定の概要
米国と日本が日本からの輸入品に対する米国の関税を15%に設定する貿易協定を発表した際、日本が米国への大規模な投資を行うとともに、米国から多量のLNGを含むアメリカ産のエネルギーを購入することも合意されました。しかし、その合意については具体的な内容が明示されなかったことから、この協定は具体的な数値目標というよりも、あくまでも方針の設定に留まるものであると捉えられていました。一方で、最近両国が署名した了解覚書(MOU)は、この協定の実施方法について新たな指針を示しています。
この新たな協定では、日本が米国に対して5,500億ドルの資金を投資することが示されています。また、この協定では日本に対し、投資対象の通知から45営業日以内に投資を行うよう求められており、守られない場合は、より高い関税が課されることになります。さらに、本協定では、投資資金の配分についてはトランプ大統領が単独で決定する権限を持つとされています。ただし、ラトニック商務長官が主導する委員会が設置され、大統領に対して投資先の選択肢を提示することになっています。
ラトニック商務長官自身も「投資先の決定権は大統領に完全に委ねられている」と述べています。また、投資先の一つとしてアラスカにおける液化天然ガスのパイプライン建設が候補となる可能性についても言及しています。その他の投資候補の分野としては、半導体や医薬品が挙げられています。投資先の最終的な決定権は大統領にあるものの、日本側の経済団体とも一定の協議が行われる予定です。加えて、投資の遂行に際しては、日本からの資材や機器が活用され、米国側は土地、水・電気等の公共サービス、インフラ等を提供することが想定されています。また、当初の発表では米国が利益の90%を得るとされていましたが、了解覚書では利益を両国で均等に分配すると記載されています。なお、このプログラムはトランプ大統領退任前日の2029年1月19日で終了する予定です。
投資協定がもたらす経済的な影響
この協定にはいくつかの課題が存在します。第一に、対米直接投資が大幅に増加した場合、米国の貿易赤字が拡大することが予想されることです。米国の経常収支赤字(主に貿易赤字)は、米国の(国際収支の旧基準[BPM5]における)資本収支黒字によってほぼ相殺されています。この資本収支黒字とは、米国への純資本流入を指します。米国が輸出収入よりも多くの金額を輸入に支出した場合、その資金は外国からの投資として米国に還流します。もし資本収支黒字が増加すれば、経常収支赤字も拡大することになります。【訳者注:現行の国際収支統計[BPM6]において、資本収支の項目は、資本移転等収支と金融収支に変更されており、対米直接投資の増加は金融収支の負債増(非居住者からの投資増)として計上されます。その際に工場建設等で米国外の資材の調達が増えれば、輸入増加による貿易赤字の拡大につながる一方、その工場の製品が輸出されれば、貿易赤字の縮小につながります。したがって、経済的な影響はそのタイミングも含めて、幅を持ってみる必要があります】
第二に、市場経済においては、投資規模は資本の需給や投資家が期待する収益率に基づき決定されます。今回の協定により、市場が決定する水準を超えて投資が増加した場合、その他の条件が一定であれば投資収益率が低下することになります。加えて、米国では失業率が低水準で推移し、慢性的な人手不足が続いているため、大規模な新規投資プロジェクトに必要な労働資源が十分に確保できるかは不透明です。
第三に、米国政府が資本の配分を決定することは、市場原理に基づく資本配分システムからの逸脱を意味します。これは、最近米国が公的企業に対し資本を投入し、今後も同様の政策の拡大を約束していることとも通じる動きです。
第四に、この了解覚書(MOU)は法的拘束力のある契約ではなく、単なるロードマップに過ぎません。そのため、両国のいずれかが協定の一部を順守しない決定を容易に下すことができます。このため、より確かな法的基盤が整備されない限り、両国の企業の中には協定への参加を躊躇するところがあるかもしれません。
一方、2025年の最初の7カ月間における日本から米国への海外直接投資(FDI)は、前年同期比で20%増加しました。これは、日本全体のFDIが4%の増加に留まる中での動きです。2025年7月単月では、全体のFDIが10%減少した一方、米国向けのFDIは19%増加しました。
2025年の最初の7カ月間において、日本からのメキシコへのFDIは前年同期比で21%減少しました。これは、日系企業が米国とメキシコの経済関係の今後に対して楽観的ではなくなっていることを示唆しています。日本からメキシコへの投資の大半は、米国向け輸出能力の開発を目的としています。一方で、日本から中国へのFDIは6%減少しており、その背景には米中関係の悪化が影響している可能性があります。
このような対米投資の急増は、日系企業が米国の貿易規制によるリスクを低減させる意図によるものと考えられます。一部の日本企業は、今後も高関税政策が続くと見込んでおり、サプライチェーンを米国へ移すことでリスクを抑えようとしているようです。
※本記事と原文に差異が発生した場合には原文を優先します。
Deloitte Global Economist Networkについて
Deloitte Global Economist Networkは、デロイトネットワーク内外の視聴者向けに興味深く示唆に富むコンテンツを発信する多様なエコノミストのグループです。デロイトが有するインダストリーと経済全般に関する専門知識により、複雑な産業ベースの問題に高度な分析と示唆を提供しています。デロイトのトップマネジメントやパートナーを対象に、重要な問題を検討するレポートやThought Leadershipの提供、最新の産業・経済動向にキャッチアップするためのエクゼクティブブリーフィングまで、多岐にわたる活動を行っています。