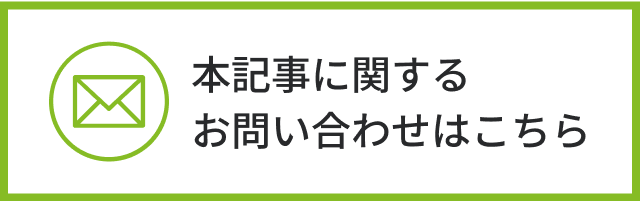M&Aとは――M&Aのトレンドを理解するための切り口
M&A(Merger & Acquisition=統合と買収)と一口に言ってもその形態は様々である。株式を取得することで企業の支配権を獲得する株式譲渡は最も典型的なM&Aの形態であるが、買収対象が法人ではなく企業内の一事業部門である場合には、単純な株式譲渡ではなく事業譲渡や会社分割を経たうえでの株式譲渡の形態をとる。また、経営統合の際には共同株式移転、株式交換、吸収合併などの形態が採用されるケースもある。
多様な形態にかかわらず、共通している点としては、対価の支払を伴う企業活動の支配権の獲得(一部支配権の獲得を含む)が生じることであり、現代におけるM&Aの定義は、字面よりも広い概念を含むものとなっている。
.png)
M&A市場
M&A市場の定義には複数の分類があるものの、主に当事者の所在国に基づく分類により分析されるケースが多い。具体的には、日本の企業同士のM&Aを国内取引(IN-IN)と呼び、日本企業が海外企業を買収するM&A をアウトバウンド取引(IN-OUT)、海外企業が日本企業を買収するM&Aをインバウンド取引(OUT-IN)と呼ぶ。
国際化の進んだ日本企業においては外国株主の割合も多くなっていることから、国内・海外と切り分けて理解することが適切ではない案件もあるものの、国内の合従連衡、海外進出という経済動向を踏まえてM&A市場の大きなトレンドを観測する目的から、典型的な分類方法として採用されている。
業種
どの業種でM&A が活発であるかはM&Aトレンドを理解するうえで重要である。当該業種の業界再編がどの程度起きているのかを踏まえ、業界内での競合状況から今後を予測するうえで参考とするためである。
また、例えば、近時においてテクノロジー企業と伝統的な業種の企業との間で新しいビジネスモデルを模索するために業種を跨ぐM&Aも活発となっているなど、対象会社のみでなく買収会社の業務を併せて把握することが、M&Aトレンドの背景を理解する観点からは有益である。
プレーヤー
M&Aのプレーヤーは大別して2種類存在する。自己の事業の拡大のための買収、グループ内事業の再編・ノンコア事業の売却などを通じて全体の事業価値を高めていく事業会社(Strategic Investor)と、対象事業を定めて投資し、当該事業価値を高め、売却(Exitとも呼ぶ)することによって収益を獲得するプライベートエクイティファンド(Financial Investor)である。
プライベートエクイティファンドは、投資後に投資先企業自身によるM&Aを支援し、その企業価値を高めたうえで売却することを志向するケースが多く(ロールアップと呼ぶ)、各業界内におけるM&Aを促進させる役回りを産業構造上担っている。日本での活動が活発化し出した2000年代初頭においては、企業再生を担った一部ファンドが「ハゲタカ」と呼ばれ警戒される風潮もあったが、近年においては実績の積み上げ・ファンド規模の拡大・認知度の向上に伴い、M&A市場における担い手としての存在感を高めている。
公表時期
一般的にM&A案件の存在を知るのは当事者の発表時点であるが、発表のタイミングは案件事情により様々である。当事者がM&A取引を履行した時点(クロージングと呼ぶ)だけでなく、株式譲渡契約や事業譲渡契約などの最終契約書が結ばれた時点、さらにさかのぼって基本合意書(売り手と買い手との間で買収に関する基本的な事項について合意に達した際に交わされる書面)を交わした時点で公表されるケースもある。
発表のタイミングは当事者の合意により定められることが多いが、当事者に上場企業が含まれる場合には一般株主の利益保護の観点から証券取引所における適時開示の基準に基づき決定される。
M&A 金額
M&A 案件の規模を示す金額は必ずしも公表されるものではないが、当事者のいずれかに上場企業が含まれ、その関連当事者に対する説明責任の観点から、特に当事者の財務などに影響を与える可能性が高い案件などを中心に公表される(こちらも証券取引所における適時開示の基準に基づく)。
M&A案件に係る金額には大きく分けて2種類あり、実際に当事者間で決済された取引金額(Transaction Value)と、対象会社自身が負っている純有利子負債(一義的には借入金残高から現預金残高を控除した金額)を含む企業価値(Enterprise Value)がある。また、現金に代えて買収会社の株式を対価とする株式交換や合併の場合にも、当事者のいずれかに上場企業が含まれればその時価総額に基づく取引金額が算出される。
2021年の日本のM&A の動向
.png)
概要
2021年の日本企業によるM&A件数は4,280件と過去最多水準となった。一方、市場別内訳では、IN-IN 3,337件、IN-OUT 625件、OUT-IN 318件であり、IN-IN案件が全体に占める割合が8割程度と過去10年において最も高い水準となった。公表された金額総計は16兆4,844億円であり、うちクロスボーダー(IN-OUT、OUT-IN)案件の占める割合は8割超となった。
過去10年間、堅調に右肩上がりで件数を増加させてきた日本企業によるM&Aは、2020年においてはCOVID-19による経済活動の鈍化の影響を受け件数を減らしたものの、2021年においてはその復調が鮮明となった。
そして、特筆すべきはIN-IN案件=国内案件の件数割合の多さである。公表された金額総計においてはクロスボーダー案件の占める割合が非常に高い一方、件数割合においては国内案件が多いのは、金額が非公表の、事業承継などを背景とした国内中小企業を対象とした案件が活発であるためである。これは継続的なトレンドであったが、2021年においては国内案件の件数割合の増大が著しい。要因としては、COVID-19による移動制約などを背景とした日本企業による投資資金の国内回帰、景況感悪化を踏まえた国内企業の合従連衡の加速などが想定される。日本経済全体の大きなうねりがM&Aトレンドにも影響を与えていると見ることが可能だろう。
近時の傾向――日本企業の構造改革・投資ファンドの躍進
近年の大手日本企業におけるM&Aの特徴の1つとして、構造改革のためのM&A、つまり事業の選択と集中に基づく売却および買収が活発化していることが挙げられる。2019年6月28日に経済産業省が発表した「公正なM&Aの在り方に関する指針」の中でも指摘されていた親子上場企業の再編が、2022年4月に予定されている東京証券取引所の再編をきっかけとして加速しており、2021年においても、ベインキャピタルによる企業コンソーシアムによる日立金属の買収、そして、凸版印刷によるトッパン・フォームズの完全子会社化 など、グループ関係の解消・一体化を目的とした買収案件が目立つ結果となった。
また、投資ファンドの躍進が目覚ましかったことも2021年を代表する特徴であろう。日本企業に対する投資会社によるM&Aの件数は1,035件となり過去最多記録を更新した。この件数増を牽引しているのは、事業会社によりベンチャー投資などを目的として組成されたCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)であり、約7割程度を占めている。公表金額においては8割を占めている外資系投資会社勢は、日本企業の構造改革の受け皿として機能しており、先に挙げたベインキャピタルの例の他、KKRによる弥生の買収 なども2021年の代表的案件となっている。
おわりに
2021年はCOVID-19により日本企業の構造改革という潮流が一段と加速された年であった。事業を構築するための"時間をカネで買う"行為ともいわれる、M&Aはその手段として過去にも増して活用されている。そして、国内における投資ファンドの市場規模などは欧米に比してまだまだ低い水準である。日本企業ひいては日本経済の構造改革と、最適な資本投下を求める投資家の要請とが両輪となって、今後もM&Aの活発化を継続させていくものと見込まれる。第2回は経営戦略とM&Aと題してお送りする。