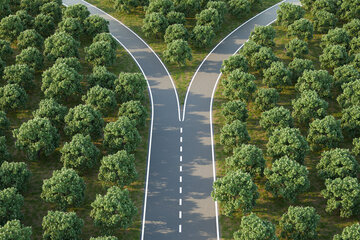米国の対中政策の転換
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
増島 雄樹
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
バリュエーション&モデリング
上田 翔一

景気循環による経済的影響は企業にとって不可避なものです。しかし、世界および地域経済に対し長期的な見通しを持つことにより、企業は景気循環のリスクを最小化することができます。デロイトは、世界のビジネスリーダーたちに必要な、マクロ経済、トレンド、地政学的問題に関する明快な分析と考察を発信することにより企業のリスクマネジメントに貢献しています。
本連載では、デロイトのエコノミストチームが昨今の世界経済ニュースやトレンドについて解説します。今回は、Deloitte Insightsに連載中のWeekly Global Economic Updateの2025年8月18日週の記事より抜粋して日本語抄訳版としてお届けします。
目次

Ira Kalish
Deloitte Touche Tomatsu
チーフエコノミスト
経済問題とビジネス戦略に関するデロイトのリーダーの1人。グローバル経済をテーマに企業や貿易団体への講演も多数行っている。これまで47の国々を訪問したKalish氏の解説は、ウォール・ストリート・ジャーナル、エコノミスト、フィナンシャル・タイムズなどからも広く引用されている。ジョンズ・ホプキンス大学国際経済学博士号取得。
ハイテク製品の輸出制限緩和
近年、米国政府は中国に対し、先端半導体やその製造装置など重要な技術の輸出を制限してきました。その目的は、中国が米国の覇権を脅かす軍事能力を得ることを阻止することにありました。この政策は第1次トランプ政権、さらにバイデン政権でも継続され、超党派の支持を得ていました。
しかし現在、第2次トランプ政権では異なるアプローチを採用しています。主要品目の輸出を制限するのではなく、輸出企業が米政府に手数料を支払うことを条件に、一部ハイテク製品の対中輸出を認める方針へと転換しました。政府は、「中国が最先端技術を入手できないよう、技術水準を落としている」と説明していますが、政権の批判派は「新しいアプローチでも、依然として中国の軍事能力向上につながってしまう」と警鐘を鳴らしています。米国連邦議会下院・中国特別委員会の共和党委員長は、「輸出管理は国家安全保障を守る最前線の防衛手段であり、中国のAI能力を強化する技術の販売を政府が許可するような前例を作るべきではない」と主張しました。これに対し政権側は、新たな政策は米国の輸出拡大に資するものであるとして正当化しています。
アジア諸国への高率関税による逆効果
一方、米国は企業に近隣のアジア諸国への投資を通じた対中依存リスクの軽減を促してきましたが、それらのアジア諸国に課した高関税はその狙いとは反する効果をもたらしているようです。東アジア諸国に課す高関税は、これらの国々と中国の経済的・政治的関係を強化する要因となっています。一方、中国に対する高関税は、中国への海外直接投資(FDI)の急減につながっています。2025年第2四半期のFDIは87億ドルと、2022年第1四半期に記録したピーク時の10%未満まで落ち込みました。
インドとの関係悪化
米国と関係が悪化しているように見える国の一つが、インドです。インドがロシアからの原油輸入を継続していることを理由に、米国はインドからの輸入に高関税を課しました。その影響により、インド国内では米国製品の不買運動が始まっています。米国にとって、インドはアジア太平洋地域で拡大する中国の地政学的影響力を抑えるための重要な存在とみなされてきました。そのため、現在のインドに対する対応は、一部で疑問視されています。
※本記事と原文に差異が発生した場合には原文を優先します。
Deloitte Global Economist Networkについて
Deloitte Global Economist Networkは、デロイトネットワーク内外の視聴者向けに興味深く示唆に富むコンテンツを発信する多様なエコノミストのグループです。デロイトが有するインダストリーと経済全般に関する専門知識により、複雑な産業ベースの問題に高度な分析と示唆を提供しています。デロイトのトップマネジメントやパートナーを対象に、重要な問題を検討するレポートやThought Leadershipの提供、最新の産業・経済動向にキャッチアップするためのエクゼクティブブリーフィングまで、多岐にわたる活動を行っています。