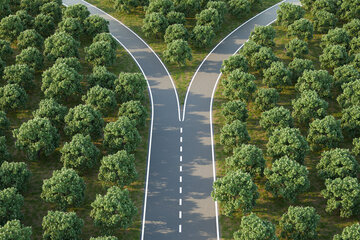NEC×デロイト トーマツ、ブランド価値評価の取り組み(前編)
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
川端 一成

ブランド価値の定量化を実現化させるデロイト トーマツのサービスについて語られた連載第一回。それを受けて、第二回となる今回は具体的な事例を紹介していきます。125年の歴史を持つグローバルテックカンパニーであるNEC。彼らと協働したブランド価値可視化、向上のためのプロジェクトはどのようにスタートし、進んでいったのか。可視化へのチャレンジと、可視化できたことによるこの先の展望とは。NECメンバーにざっくばらんに本音で語っていただきました。
目次
見えないものにこそ無限の可能性がある。
——NECは元々ネームバリューのある企業だと思います。なぜ、ブランド価値可視化に取り組まれたのでしょうか。

角谷(NEC 経営企画・サステナビリティ推進部門 ブランドエクイティエグゼクティブ)
確かにNECはこれまで積み上げてきたネームバリューを一定保持していると思います。ただ、ネームバリュー、いわゆるブランド価値が成長しているのか。世代が変わっていく中で今後も持続可能なのか。また、それが企業の持続的な成長にどのように貢献できているのか。こうした問いが必ず出てきます。弊社でもそうです。製造業から社会インフラ・ITサービスに事業を転換してきた中で、NECという企業を正しく社会に認識してもらうためには、ブランドがますます重要になってきます。そうした中で、持っている資産を最大限活用し企業価値向上を実現するためにも、ブランドという見えない資産を可視化し、社員の自律的な活動につなげ、価値に変換し、それを経営に活かすための仕掛け・仕組みづくりを行っていかなければいけません。ブランド含め、見えないものにこそ無限の可能性があると思っています。
ブランドが企業価値に貢献することの証明
——ブランド価値可視化プロジェクトを立ち上げるに至った経緯と意義について教えてください。

角谷
2022年、それまでNECにはなかった「ブランド」と名のつく統括部が立ち上がりました。以降、企業ブランディングにまつわる様々な活動を展開しましたが、先ほど述べたように、経営陣からは「活動自体は理解するが、各活動がそれぞれどのように企業価値向上に結びつくのか」と問われ続けていました。そうした背景もあり、新たにブランドエクイティグループ(現・ブランドエクイティマネジメント室)を設置、企業価値算出と同じ管理会計をベースに、ブランド価値を可視化、定量化の可能性を探るチームを整えました。

長谷川(NEC 経営企画・サステナビリティ推進部門 ブランドエクイティマネジメント室長)
私たちは常にブランド活動の意義を問われていましたが、活動の先にあるブランド価値を数字で示せることには大きな意味があると思っています。ブランド価値を可視化し現状を把握すれば、おのずと課題も明らかになります。現状と課題が把握できると自然に社員の反応が変化してアクションが生まれ、アクションを起こしていく中でブランドに対する理解もさらに深まっていくでしょう。理解が深まれば深まるほど、ブランドに投資価値があるのかといった議論は少なくなっていき、むしろ「これから何をするべきか」というポジティブな議論が増えると思います。
パートナーとしての信頼と伴走型での支援
——今回のプロジェクトを推進する際、デロイト トーマツと協働することを選んだのはなぜですか。

長谷川
もともと、ファイナンシャルのアドバイザリーとしてお付き合いがあり、パートナーとしての信頼がありました。もちろんコンサルティングもお任せできますから、その力をお借りすればブランドを金銭価値で表現できるかもしれないと考えご相談しました。相談する中で、私たちには監査やM&Aの知見がなかったため、そこに強みを持つデロイト トーマツのご支援をいただけることが大きなポイントでした。また、ブランド価値の可視化という新しい領域のチャレンジであったことに加え、単に発注してアウトプットを納品いただくという形のプロジェクトではなく、私たち自身も算出のロジックや考え方を理解することが重要だったので、伴走型でご支援いただけるかどうかといった点も決め手でした。
——後半でプロジェクトの具体的なお話がありますが、今回のプロジェクトでのポイントはどこでしたか?

角谷
まず当然ですが、ブランド評価を金銭価値で表現しきったことが何よりも大きなポイントでした。金額価値にできたことで、次の一手が打てるようになりました。例えば金額価値が1,200億円と算出できたとして、それだけでも大きな成果ですが、そのまま社員に伝えても金額が大きすぎてピンときません。であればどうすればより自分ごと化してもらえるかを考えます。私たちは独自の工夫で金額価値を一人当たりのブランド価値創出額として落とし込みました。120万円なら自分ごととして捉えられますし、120万円を240万円にするには自分がどのような活動をすれば良いか検討するようになると考えたからです。見えないものを可視化し、それをアクションにつながる形に落とし込み浸透させる方法を探る。ブランドを自分ごと化し、一人ひとりがブランドに対する意識を変えるきっかけを作れたと思います。