
AI技術が急速に進展していますが、ビジネスの現場で最大の課題となっているのが、AIを使いこなすための人材やスキルの不足です。AI領域の教育や開発支援などを専門とするデロイト トーマツ ディープスクエア株式会社(以下DTDS)代表の小林(寛)とCTOの小林(範)に、必要とされる人材像などについて話を聞きました。
AI人材不足が最大の課題
AIの利活用においては、人材不足が常に課題の筆頭にあがります。デロイト トーマツ グループが2025年8月に発表した調査結果(※1)でも、「PoCやトライアルの段階から生成AIの本格的な開発・導入に取り組む際の課題」の回答で最も多かったのは「専門人材の不足」で45.1%となりました。企業の実態をどのようにご覧になっていますか。
.jpg)
小林(寛)
人材育成への投資は進んでいますが、依然として量・質ともに十分とは言えません。AIに関する代表的な資格試験の1つが一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)の検定試験で、DTDSは資格認定プログラム事業者です(※2)。基礎知識と事業活用能力を検定するG検定とディープラーニングの理論の理解と開発実装能力を認定するE資格があります。量に関してみると、G検定の合格者は累計11万人、一方でIPA(情報処理推進機構)が行うITパスポートは200万人です。これは、AIに関する専門知識を備えた人材が、ビジネスパーソン全体の中はもとより、IT人材全体でもまだごく少数であることを示しています。質に関する指標として、三菱商事がG検定を全社員必修とし管理職の昇格要件と決めたことが注目されます(※3)。今後、AI知見を前提とする企業は増えていくでしょう。
生成AI時代のAI人材ニーズの変化
ChatGPTの公開が2022年、JDLAの検定はそれ以前の2018年からスタートしています。生成AIの登場以降、AI人材へのニーズは変化していますか。
.jpg)
小林(寛)
以前は、AIはエンジニアやデータサイエンティストなど専門家が扱う技術でした。しかし、生成AIの登場により、誰もがインターネットを使うような感覚で高度なAIを扱えるようになったことは画期的です。企業の関心も「AIを活用できる人材」へと大きく変化しています。

小林(範)
組織内のAI人材には3つのタイプがあるといえます。①AIをどうビジネスに活用するか企画・推進する人材と、②現場に導入されたAIを実際に活用する人材、③AI技術の開発や実装を担うエンジニアです。①の人材育成のために創設されたのがG検定、③がE資格で、その位置づけは設立当初から変わっていません。G検定を通じて、AI技術に関するベーシックな知識や、関係する法律や契約、倫理やガバナンスなどの知識を得ることができます。E資格はディープラーニングの実装を行うエンジニア向けの資格試験です。生成AI登場後は、②の層、すなわち現場でAIを活用する人材の裾野が大きく広がっています。その結果、AIへの関心の高まりとAI導入促進につながり、①人材の需要も急拡大しています。③エンジニアについても、生成AIの根幹技術はTransformerに代表されるディープラーニングですから、ディープラーニングの知識や技術を具備することは、今後もキャリアの強みになっていくでしょう。生成AIによってノーコードが進展し非エンジニアでもアプリ開発が可能になってきましたが、本質的な技術理解の重要性は変わりません。
生成AIは誰でも利用できるとはいえ、導入してもビジネス利用が進まないという企業は多いように見受けられます。効果的に利用を促進するための施策はありますか。
.jpg)
小林(寛)
具体的なユースケースに触れることが重要です。「AIを使えば業務がどう変わるのか」を、実体験として感じてもらうことは有効です。例えば、業務改善のアイデアコンテストや生成AIを使ったハッカソンの開催なども有効です。生産性向上や効率化を達成したことにインセンティブを与え、従業員がAIを使わざるを得ない、自ら使いたくなる環境を作るのです。多くの企業とAI活用について話をしていますが、トップダウンとボトムアップは両方重要だと感じます。トップダウンで変革を推進すれば、企業全体に活用がいきわたります。現場がAIに関心を持ち使いたいと思うことは重要ですが、それだけでは部分的な改善に留まります。

小林(範)
経営層の方々も自らAIに携わり、理解を深めていただきたいですね。経営層の方々が生成AIを体験し、理解し、戦略に組み込む姿勢があることで、組織全体の関心と実行力が高まります。
AI活用促進のための施策とガバナンス
安心して利用できることも重要です。リスク対応やガバナンスへの対応はどうすれば良いでしょうか。
.jpg)
小林(寛)
政府や団体がAI利活用のガイドラインを公開しています(※4)。それらを自社向けに適切にカスタマイズして利用すると良いでしょう。しかし実態としては、きちんと整備できていない企業も多いように見受けられます。

小林(範)
企業がルール設定やセキュリティなど対策をしたうえで自前のAI基盤を整備している場合は従業員も安心して利用できるでしょう。ただし独自環境の構築にはコストがかかります。中小企業などでは汎用LLM(ChatGPTやGemini等)を業務で直接使うケースも増えていますがそのまま使うのは、やはり様々なリスクがあります。機密情報の扱いや著作権への対応、出力に対する責任の所在などを定義した明確なルールが不可欠です。
AI人材育成の課題と今後の展望
AI人材を育成する際の課題についてもコメントをいただけますか。
.jpg)
小林(寛)
AI人材とビジネスの連携は課題になっています。AI人材育成に投資し、研修受講者や資格取得者何人を達成する、という目標は立てやすいです。しかし人材を育成した成果として、具体的にどういう業務改善や生産性向上が起きているのかまで考え、費用対効果を明らかにする必要があるでしょう。

小林(範)
AI人材の活躍によって、既存のビジネスモデルを大きく変革すると、従来の業務が不要になる場合があります。これは、日本企業にとって非常に踏み込みづらいテーマでもあります。AI導入やAI人材育成は進みつつありますが、既存ビジネスの変革まで見据えている企業は多くないのが実情です。
.jpg)
小林(寛)
AIには変革を起こす力がありますから、活用が遅れると国際的な競争力を失いかねません。過去、技術の発展とともに電話交換手やタイピストという職業がなくなったのと同じように、 AIによって置き換えられる業務も確実に増えていきます。AIを活用すると必要となる業務やスキルが変わるので、AIで代替できる業務に携わっていた人材はリスキリングし、新たな成長領域に配置転換するなど、戦略的な人材育成を行う必要があるのではないでしょうか。
この後、AI時代の企業戦略や人に求められる役割とは、という議論に発展しました。引き続き、対談記事を掲載します。
<参考>
※1:デロイト トーマツ グループ「プライム上場企業における生成AI活用調査」(2025年8月)
https://www.deloitte.com/jp/ja/about/press-room/nr20250828.html
※2 一般社団法人日本ディープラーニング協会 資格試験について
https://www.jdla.org/certificate/
※3 三菱商事、AI資格を管理職の昇格要件に 全社員必修へ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC09CPU0Z00C25A4000000/
※4 総務省「AI利活用ガイドライン」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000809595.pdf
経済産業省・総務省「AI事業者ガイドライン」
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/20240419_report.html
一般社団法人日本ディープラーニング協会 生成AIの利用ガイドライン
https://www.jdla.org/document/#ai-guideline
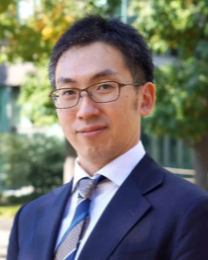
小林 寛幸
デロイト トーマツ ディープスクエア株式会社
代表取締役社長

小林範久
デロイト トーマツ ディープスクエア株式会社
代表取締役/CTO





