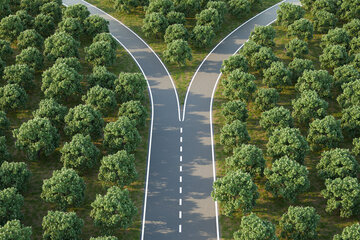生成AI時代のカスタマーサービスとCX向上
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
DTFAインスティテュート
小林 明子

AIの進化がカスタマーサービスやコンタクトセンターの現場をどう変えるのか。業務プロセス改革、リスク対策、ROIの考え方など、AI活用でCX(顧客体験)向上を成功させるための視点について、DTFAのプロフェッショナルである加瀬と松田がクライアント事例や最新動向をもとに語りました。
目次
AI導入における企業の課題と現状
カスタマーサービスやコンタクトセンターなど、顧客対応はAIとの親和性が高い領域で、顧客事例も増えつつあります。日々クライアントと接しているお二人に、AIを活用したCX向上についてお話を聞きたいと思います。まず、AI活用に関しては、どのような課題を持っている企業が多いですか。

加瀬 剛峻(マネジャー)
生成AIの発展を受けて、どの企業もAIの利活用には積極的です。既に、大企業の大多数が何らかの形でAIを導入しています。ただし、利用実態を見ると、PoC止まりになっていたり、現場担当者がAIに個人情報などどこまで入力していいのか判断できなかったりで、導入しても利用されていないAIが既に生まれているケースもあります。

松田 汎未(シニアコンサルタント)
実際に話を聞くと、AIをビジネスにどのように適用し何の成果を得たいか曖昧で、活用イメージを明確に描けていない企業もありました。目的が曖昧で、リスクに慎重になりすぎてしまうと、利用が進みにくくなります。
AI活用場面の多様化と技術進化
CX向上を図る上でに何ができるか、具体的に知っておくことが重要になりそうです。実際には、顧客対応の様々な場面で、が活用できるのではないでしょうか。

松田
その通りです。チャットボットやボイスボットによる応対も生成AIで技術が進化しています。従来型のIVR(電話の自動音声応答システム)は、音声ガイダンスにしたがってダイヤルをプッシュしオペレーターにつなぎますが、ボイスボットを利用すれば、顧客が電話をかけると機械が音声で回答し、会話の中で必要な手続きなどを完了させるなど、人へのエスカレーションを減らすことができます。オペレーターの通話に関しても、内容を音声認識でテキスト化し、生成AI技術で要約を作成できます。コンタクトセンターソリューションはAIの活用が進んでおり、通話相手の契約内容や過去の問い合わせに基づき、リアルタイムにパーソナライズした回答をサジェストしたり、音声から感情を読み取り、どのタイミングで顧客が怒ってクレームになったか分析を行ったりするなど、高度化が進んでいます。顧客の声(Voice of Customer)のデータ収集と分析の精度が向上するため、VOC分析の活用も加速しています。

加瀬
実態を見ると、大手企業でもかなりアナログな業務を行っている事例もありました。電話の記録はオペレーターが都度入力しますが記憶の間違いや漏れもあり、問題が起きれば管理者(SV:スーパーバイザー)が記録や録音をチェックするといった状況です。このケースでは通話の自動文字起こしと要約生成で多くの課題を解決できました。
AI導入の戦略とリスク対策
技術は高度化している一方で、足元には解決すべき課題もあるという状況ですね。どのようにAIを導入すると効果的か、見定めるためのアドバイスはありますか。

加瀬
AIは目的ではなく手段です。現在の業務ありきでAIを使おうとするのはなく、効率化、省力化、データ利活用などを実現するために、戦略を持って導入することが重要です。先ほど挙げた顧客事例では、経営層にはAIで改善できるだろうという期待がありましたが、実際に何が有効か、ユーザ起点での課題解決を重視しました。通話の記録が正確に残っておらずトラブルが起きており、顧客対応を担当するメンバーにはITが不得手な年配者もいました。現場の負担を増やさず自動的に記録を残し、データを活用できる形で管理できるソリューションを提案しました。
ハルシネーションや情報漏洩など、リスクに対する懸念にはどのように対応していますか。

松田
ポリシーやルールを制定し、ガバナンスを構築することは必須です。私たちは顧客の要件に合わせて、機密情報や個人情報の扱い、ユーザから取得したデータの利用可能範囲、AI事業者のデータセンターの立地は国内か海外か、AI事業者の契約条件など細部まで確認します。データセンターが国内でもデータ処理の際に海外リージョンを利用する場合があったり、AI事業者がユーザのデータを見る権限を持つ条件になっていたり、様々なケースがあります。

加瀬
生成AIからハルシネーションをなくすことはできませんが、リスクを回避するよう業務フローを設計します。AIのアウトプットを必ず確認する工程を入れる、判断が伴う部分は人にエスカレーションするなど、AI任せにしない、誤りが起きた際にAIの責任にしないことに留意します。
AIによるCX向上のROI測定、成功に導くポイント
AI導入においては、常に費用対効果が問われるのではないでしょうか。ROIの試算や測定はどのように考えればよいですか。

松田
AI導入効果として分かりやすいのは時間の削減です。例えば、音声認識による文字起こしと要約の自動入力で、電話応対後のオペレーターの後処理作業(ACW)を大幅に削減することができます。また、回答のサジェストでより迅速かつ的確に対応できるようになれば、通話時間自体も短縮できるでしょう。対応できる顧客の数が増え、オペレーターの稼働率も高まります。CX向上に寄与するKPIはほかにもあります。電話の待ち時間や対応時間を削減し、回答間違いやクレームにつながる対応が減れば、顧客満足度が高まります。さらに、人手不足に悩むコンタクトセンターは多いですが、AIの支援により業務の難易度が下がりクレーム対応などの精神的な負担が軽減されれば、人員を確保しやすくなるのではないでしょうか。
AI活用について、現場の知見に基づいた具体的なアドバイスを頂きました。最後に、CX向上を成功に導くために、コンサルタントとして重視していることはありますか。

加瀬
AI活用の機運は高まっており、経営者は、CXを向上させ企業の競争力を高めたいと前向きに考えています。ただし、経営レベルでは、実は業務プロセスがアナログでデータの品質も悪いといったような、現場のリアルな問題を理解することは難しいでしょう。クライアント企業を支援する際は、業務側のキーパーソンから現場課題を正しく把握し、経営層と課題感を共有し、両者にAI導入イメージや導入効果を解像度高く示せるように心掛けています。トップダウンの意向とボトムアップのニーズの接点を見つけることは、私たちの役割の一つだと考えています。

加瀬 剛峻
マネジャー
日系製造業にて企画、マーケティング、営業などの業務を経験した後、2022年にDTFAへ入社。大型プロジェクトや新規事業立案、AI活用による業務改革のコンサルティング、M&Aアドバイザリーやデューデリジェンスなど、幅広い分野を担当している。

松田 汎未
シニアコンサルタント
日系総合コンサルティングファームにて自動車メーカーへの業務改革支援、中央省庁および電気工事会社へのBPO支援などを経験した後、2025年にDTFAへ入社。AI活用による業務改革のコンサルティング、デューデリジェンスやPMIなどを担当している。