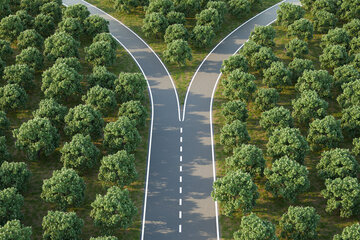官民から見た、中堅企業の成長の可能性と課題(後編)
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
コーポレート ファイナンシャルアドバイザリー
西本 雅代

2025年2月6日、高い成長可能性を有する「中堅企業」にフォーカスした「Deloitte Private / 朝日新聞社 中堅企業フォーラム」が開催されました。官と民、それぞれの視点から中堅企業の「成長」と「挑戦」をテーマとした基調講演およびパネルディスカッションが行われ、中堅企業の可能性に多くの参加者が関心を寄せました。レポート後編となる今回は「中堅企業の更なる成長」と題したパネルディスカッションの様子をお伝えします。
目次
<モデレーター>
関根 和弘氏
朝日新聞社 GLOBE+編集長
1998年、朝日新聞入社。徳島支局を振り出しに、福山(広島県)、神戸両支局を経て大阪社会部。モスクワ大学ジャーナリズム学部に留学したあと大阪社会部に戻り、モスクワ支局へ。ソチ五輪やウクライナ政変、クリミア併合などを現場で取材。帰国後は北海道報道センターで北方領土問題などを担当し、2017年から2年半、「ハフポスト」の日本版に出向。デジタル編集部、GLOBE+副編集長を経て2022年9月より現職。
<パネリスト>
河野 太志氏
経済産業省 経済産業政策局 審議官
1996年に東京大学法学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)入省。製造産業局自動車課長、内閣総理大臣秘書官、資源エネルギー庁長官官房総務課長などを経て、2024年7月から現職。
藤森 義明氏
シーヴィーシー・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 最高顧問
東京大学工学部卒業後、1975年に日商岩井(現・双日)に入社。1997年には米GEへ。2001年、アジア人初となるシニア・バイス・プレジデントに抜擢される。2008年、日本GE取締役会長 兼 社長 兼 CEOに就任。2011年には株式会社住生活グループ(現・LIXILグループ)の取締役代表執行役社長 兼 CEOに就任し、グローバル企業への飛躍をけん引した。現在は、武田薬品工業 社外取締役や日本オラクル株式会社 取締役会長などを務めている。
久世 良太氏
株式会社サンクゼール 代表取締役社長
2002年に入社したセイコーエプソン株式会社を経て、2005年より株式会社斑尾高原農場(現・サンクゼール)へ。経営サポート部部長や専務取締役などを経て、2018年より現職。
古田 温子
デロイト トーマツ エクイティアドバイザリー合同会社 代表執⾏役社⻑
大手証券会社、IR/SRコンサルティング会社の取締役、経営人材コンサルティング会社のパートナーを経て、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社(DTFA)に入社するとともにデロイト トーマツ エクイティアドバイザリー合同会社(DTEA)で現職に就く。これまでに敵対的買収防衛支援、プロキシーファイト対応、アクティビスト対応、中期経営計画策定支援、経営幹部育成、幹部社員アセスメントなどのアドバイザリー業務に従事した経験を持つ。
ディスカッションテーマ①:中堅企業が抱える課題
モデレーター 関根:
中堅企業が更なる成長を果たすために重要な4つのテーマについてパネルディスカッションを行います。1つ目のテーマは「中堅企業の課題」です。行政の立場では、中堅企業の課題をどのように捉えているのでしょうか。
経済産業省 河野
中堅企業等へのアンケートの結果、課題として最も多く挙げられたのが人材確保でした。そのほか、研究開発や販路拡大、M&Aと回答された中堅企業等もいらっしゃいます。ただ、これはあくまで横断的な課題です。業種別に分析してみると、例えば製造業は戦略的な研究開発および設備投資、また小売業の場合は規模の経済拡大のために必要なデジタル化・M&Aのノウハウ不足などが課題として挙げられます。経産省としては、このように業種によって異なる課題をきめ細かく分析する必要があると考えています。
モデレーター 関根
河野さんからもキーワードとして出た、人材確保という課題に対してはどのようにアプローチをすべきでしょうか。
CVC・アジア・パシフィック・ジャパン 藤森
大企業の若手社員の中には「ここに居続けて良いのだろうか」という悩みを持つ人が多くいます。中堅企業はそのような人を含め、様々な人材と会い、人材プールをつくることが大切だと考えます。その上で、人材プールにいる優秀な人材に入社してもらえるように、会社としての魅力をどのようにつくっていくのか、経営陣や人事部等は考える必要があるでしょう。
モデレーター 関根
新規事業創出という課題に対しては、中堅企業の当事者としてどのように向き合っていますか?
サンクゼール 久世
自身の思いをチームに共有することを意識しています。例えば、2013年12月に立ち上げた久世福商店ブランドの開発時にも、「こういうアイディアはどうだろうか」という私の父親からのメールがきっかけで経営陣含めて議論が始まったことがありました。私自身も常に危機意識を持って市場動向やビジネスチャンスにアンテナを張った上で、気になる事柄についてはチームで話し合うようにしています。
DTEA 古田
人材確保や新規事業創出という課題は、成長戦略に関連するものですね。成長戦略を考える上では、自社の経営リソースの強みや不足を分析し、不足があるのであればM&A含めタブーなしで発想および実行ができるかどうかが重要だと考えます。
ディスカッションテーマ②:日本・地域の成長における中堅企業
モデレーター 関根
2つ目のテーマは「日本・地域の成長における中堅企業」です。そもそもなぜ行政は中堅企業にフォーカスした施策を考え始めたのでしょうか。
経済産業省 河野
いわゆる「失われた30年」の間、日本のGDPが伸びなかった要因の一つが国内投資の弱さにあります。その点、中堅企業の国内投資のパフォーマンスは良好です。加えて、売上高や従業員数も大きく伸びています。このような背景のもと、中堅企業というセクターが日本経済全体に大きな好影響を及ぼし得ると考え、日本経済が自信を取り戻す起爆剤として中堅企業をターゲットとした施策を展開しています。
サンクゼール 久世
地域経済の成長という観点でも、中堅企業の役割は少なくありません。例えば、地域産業のハブとなっている中堅企業もあります。当社についても約500社の生産者ネットワークを形成しており、連携企業との新商品の開発や販路拡大に応じた工場への投資などの経済活動を積極的に行っています。多様な企業の結節点になるのが中堅企業であり、地域経済への影響度も大きいと考えます。
モデレーター 関根
PEファンドとして、中堅企業の成長可能性についてどのように考えていますか。
CVC・アジア・パシフィック・ジャパン 藤森
中堅企業は必ず多かれ少なかれ課題を有していますが、課題があるからこそ、その課題を解決できれば成長する可能性は高くなると考えています。現に私たちの投資対象の大半が、成長期待の高い中堅企業セクターです。
ディスカッションテーマ③:ガバナンス
モデレーター 関根
3つ目のテーマは「ガバナンス」です。中堅企業におけるガバナンスの難しさについて、アクティビスト対応をされている古田さんはどのように考えていますか。
DTEA 古田
ガバナンスの舵取りは難しいと思います。例えば、未上場のフェーズでは、創業者ガバナンスがプラスに働くことが多いでしょう。スピード感のある意思決定や大胆な経営政策を実行し、成長を加速させることができるためです。一方で上場すると、東証からの要請に対応したり、株主・一般投資家の厳しい目に耐えられるガバナンス体制を構築したりと、多大なコストやリソースが必要になります。上場・非上場問わず、ガバナンスを持続的な成長に不可欠なものとして、ポジティブに捉える意識が大切ですね。
モデレーター 関根
ガバナンス強化のために、中堅企業が対応すべきことは何だと考えますか。
CVC・アジア・パシフィック・ジャパン 藤森
現状、各種指標を定量的に計測および記録している中堅企業は多くありません。一方で、ガバナンスの強化にあたってはトラッキングが必要です。そのために、経理や財務などに関する全ての指標を見える化することが重要だと考えます。
サンクゼール 久世
オーナー企業の場合、親族が後継者になるケースが珍しくありません。ただ、私は中堅企業は地域の宝だと考えます。だからこそ、優秀な経営者が次の世代に経営を担い、末長く地域に貢献するために、所有(株主)と経営の分離も検討すべきだと思います。
ディスカッションテーマ④:中堅企業の自助努力、支援
モデレーター 関根
最後のテーマは「中堅企業の自助努力、支援」です。行政による中堅企業支援の方針をお聞かせください。
経済産業省 河野
今後より具体的な施策の方向感は示していく予定ですが、業種によって異なる課題に対応する切れ目のない支援は必須だと考えています。一方で、メリハリをつけ、成長意欲がありリスクを取って勝負をしたい中堅企業へ重点的に限られた政策リソースを投下することも大切です。
モデレーター 関根
自助努力の重要性についてのお考えを聞かせてください。
CVC・アジア・パシフィック・ジャパン 藤森
行政の動きは心強く思う一方、ビジネスは「自分がリーダーだったら何をするか」という0→1の世界であり、自助努力が極めて重要です。中堅企業のリーダー達には、ぜひ中堅企業から大企業やグローバル企業への飛躍という大きな夢を持ち、自らの力を以て困難に立ち向かってもらいたいと思います。
モデレーター 関根
自助努力の重要性がよく伝わりました。
サンクゼール 久世
私も基本的には自助努力が大切だと思います。当社は2017年よりアメリカにも進出しているのですが、他の日本企業に所属する現地スタッフからは「うまくいくことはわかっているが、本社がGOサインを出してくれない」という声を聞きます。ここぞという時には投資をする意思のもとで努力をすれば、事業は成功するのではないでしょうか。
モデレーター 関根
これから飛躍を遂げようとしている中堅企業は、例えばどのような支援を検討すべきでしょうか。
DTEA 古田
未上場のうちは倒産を防ぐために出来る限りの内部留保蓄積が必要である一方、上場後は株主資本コストより負債コストの方が低いために、借り入れが求められます。上場後に財務戦略のパラダイム転換が起きるわけですね。この大転換に戸惑う中堅企業が少なくありません。必要に応じて財務の専門家からの支援を受けてみてはいかがでしょうか。