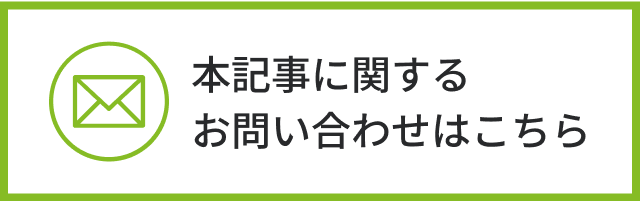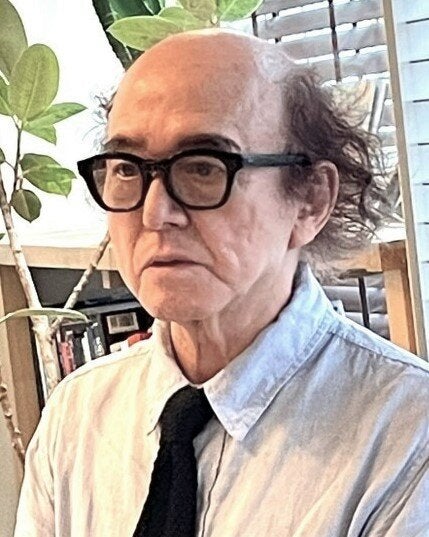
鈴木 正文氏
編集者、ジャーナリスト
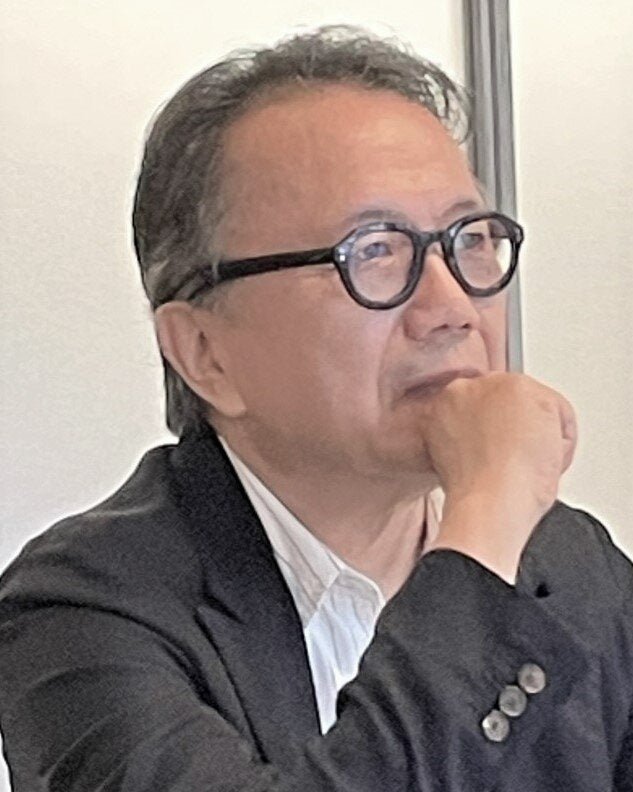
シー ユー チェン
株式会社シー・アイ・エー
ファウンダー兼取締役会長

江島 成佳
株式会社シー・アイ・エー
代表取締役社長
何も心に残らない情報が多い、現代日本の情報環境

江島
今回の鼎談では、チェンと長い付き合いがあり、GQ JAPANの編集長を約10年間務められた鈴木正文さんをお呼びしました。鈴木さんは、ファッションはもちろんのこと、長く車雑誌の編集長を務められていたこともあり、ハイカルチャーを含め様々な文化に対し大変造詣が深い方です。今回は現代日本における情報環境や編集について、お話を伺っていきたいと思います。

チェン
本日は独自のテイストとスタイルをお持ちの目利き人、鈴木さんにお話を伺えるということで、楽しみしております。まず編集の対象となる「情報」についてお聞きします。鈴木さんは現代日本における「情報の性質」について、どのような所感を持たれていますか。

鈴木
残念ながら、消費されたあとに何も残らない情報で溢れてしまっている印象です。確かに短いスパンで考えれば、有益な情報もあるでしょう。ただ、そういうものも、2~3週間後にはアウトプットをする意味のほとんどないものになってしまっているように思います。記録としてでも、かろうじて残ることができればいいのですが、そこまでもいかないような「情報」がほとんどのように感じています。
例えば、「日本銀行が為替介入をした」というニュースも、その情報を用いてFXをする人にとっては、その瞬間においては価値のある情報かもしれませんが、問題は、円の価値決定に関わるメカニズムに対する洞察にその情報が支えられているかどうかにあると思います。そうした洞察もなく、単に日銀が介入したという事実のみを報じた情報を、ここでは「情報としての情報」と定義しましょう。そういう「情報としての情報」の価値は、せいぜい1日、2日、持てばいい。
一方で、例えば、シェイクスピアや夏目漱石に対峙して得ることのできる「情報」は、「情報としての情報」とは打って変わって、深い喜びや知的満足を与えます。それは、日銀介入というような「事実」を伝えるものというよりは、僕たちが生きることに関わる「真実」をめぐる「情報」です。そうした情報を、ここでは「情報をこえる情報」と定義しましょう。僕たちにとってはどちらの「情報」もなくてはならないでしょうが、仮に無人島で生きていかざるを得ないとしたときに、より大きな価値を持つのは、「情報をこえる情報」のほうでしょうね。というか、「情報としての情報」は役に立たない。


チェン
仰る通りですね。言い換えると、人間性の欠如した、エモーショナルアタッチメントのない情報がはびこってしまっているのが、今の日本を取り巻く状況かもしれませんね。「お金になれば何次情報でも構わず発信する」「面白い三次情報・四次情報に触れていられればそれで満足」と考える人が増えてきたのでしょうね。

鈴木
物事の本質を考えないで済ませることのできる日常を送る人、送らざるを得ない人が増えたのでしょうか。その背景には、チェンさんの仰った「人間性の欠如」した日常生活や知的生活のありかたを、あたかも当たり前であるかのように捉えるばかりか、むしろそれを積極的なものとして見る風潮があるように思います。それは現代日本にとって取り組まなければならない課題だと思います。
というのも、経済効率とかコスト効率とか、それにビジネスではないはずなのに、政治や役所の仕事にさえも「効率」をアップしていくことが正しい、という観念がはびこっているからだと思います。システム効率を何であれ上げていくべきだ、という考え方ですね。けれど、人間は効率のために生きているわけではない。システムの下僕になることが人生の目的であるはずがない。そもそも人生などというものは、個人として見れば、どうせ最後には死ぬために生きているということになるわけですから、こんなに効率の悪いものはない。生きることは、出会いや別れや迷いや回り道や失恋や失望やもろもろの思い通りにならない出来事に満ちているわけで、大変に効率が悪い。しかし、だからこそ、最終的には死に身を委ねるにしても、生きることの悲しみすらが喜びにもなるわけです。効率よく生きている人がいたとして、そういう人にはどんな「人生」の喜びや悲しみがあり得るのでしょうか?
現在は、あれこれの「システム」が社会の隅々にまで行きわたって、個人は何らかの、そしていくつかの、互いにレイヤードした「システム」のパーツとして、どれだけ役立つかによって評価されていくような社会です。主人公は「システム」であって、人間ではない。人間は高速化する一方のシステムの処理スピードに合わせて生きている。瞬間、瞬間にしか価値を持たない情報を発信・消費するだけの、“情報のための情報”の奴隷として生きる人間が大量発生せざるを得ない状況があるように思いますね。でも、それは誰を幸福にすることもない間違った「システム」です。

チェン
現代は、本質的な価値を持たない三次情報・四次情報を編集して分析的なアウトプットをしていれば何となく評価される社会になってしまっている、という危機感は私も持っています。
編集ができる人は対象の聞き分けができる人

江島
少し視点を変えて、「応答性」という切り口から、日本の「情報」を取り巻く現状をひもといていきたいと思います。現在、ソーシャルメディアがコミュニケーションのプラットフォームとして広く普及しています。ソーシャルメディアは個人が意見を発信できる貴重な場である一方、対面コミュニケーションと比較して、応答性の観点では決して機能しているとは言えませんね。

鈴木
仰る通りですね。言うまでもなく、社会や人間関係は応答の連続によって成り立っています。応答するというのは、英語では「respond」です。そしてrespondの派生形が「responsibility(責任)」ですね。つまり、人は投げかけられれば、応える責任があり、社会関係とは、すなわち応答関係のことです。ところで、日本の「国会論戦」では、質問しても応えない答弁を繰り返すのが常道のようですが、それはresponsibilityの不在ですから、民主主義に責任を取っていないし、民主主義が成立していない、ということになりますね。
と、それはそれとして、一方、ソーシャルメディアでの応答関係はどうかといえば、「いいね」とか「共有」とかの形で簡略化された応答がしやすいようになっています。そうして、投げかけに対する応えが気に入らないものであったときは、そのレスポンスをブロック=拒絶することができます。つまり、応答関係を断つことができる。システム的には、自分にとって心地よいレスポンスをよこしてくれる人(アカウント)とのみ応答関係を持つように仕向けられている、といえます。もろもろのソーシャル・アカウントは動画のものも含めて、自分のコンフォタブル・ゾーンに入る情報のみが消費されていく傾向を強めることになっていくわけです。
他方、僕が長年携わってきた雑誌は、不特定多数の匿名の読者に向けて「情報のための情報」と「情報をこえる情報」を、多様な切り口=アングルで「編集」して投げかけ、読者に応答を呼びかけるメディアです。そして、読者からの応答に応答して、また読者に応答を呼びかける、というループのなかで成立するメディアであると思います。レスポンスとレスポンシビリティが生命線で、それゆえ、どんなレスポンスに対しても常に開かれていることが重要であると思っています。読者からの応答に対して責任を取れなければ、当然、読者は雑誌を見限っていく――ということは雑誌が売れなくなることを意味します。だから雑誌は、レスポンシビリティなしには成立しません。

チェン
ソーシャルメディアと雑誌の比較を、「応答」と「責任」という切り口で捉えるのは面白いですね。鈴木さんは編集に必要なものは何だとお考えですか。

鈴木
様々ありますが、「知識」というか「教養」というか、そしてさらに分野を問わない読解力がいちばん大事だと思います。編集とは、整えなければならない“何か”をどのように整えるか、という仕事です。見出しを付けたり、リード文を付けたり、どのようなエディトリアル・デザインにして、写真なり図版なりをどう配置していくかを構想したり、そしてもちろん、文章を整えることもします。ですから、取材記事なりインタビュー記事やルポルタージュやエッセイなりを、単に紙に印刷して掲載すればいいということではない。文と写真やその他のビジュアル素材の相互関係を適切に「編集」して読者に提示するわけで、文化・芸術・思想全般にわたる横断的な「教養」があればあるほど、読み応え、見応えのある誌面ができるわけです。スマホサイズにおさまる写真や余白のない画面、そして画一的な文字フォントといったデジタル・メディアの単調なプレゼンテーションに比べれば、奥行きも深ければ表情もきわだって豊かな「情報」のプレゼンテーションができる。ですから、クオリティの高い知的エンターテインメント性に満ちた情報を届けられるわけで、そうした面で「紙」の印刷メディアがデジタル・メディアにたいして持つ優位性は、いまでも少しも変わりません。デジタル・メディアの編集者もやりがいのある仕事ですが、紙のメディアを編集する仕事は、より総合的な創造性を発揮する余地があると思いますね。政治や哲学的なものも含む文化全般にわたる知識と教養がとても大事というか、そういうものがよりよく生かせる仕事だと思います。

江島
編集ができる人は、教養人であることが求められる?

鈴木
そうですね。編集とは現実に対する人間的な応答の1つの形です。応答し得るためには「対象=現実」が発している声や音階を聞き分けることができなければなりません。解像度の高い「耳」と「眼」と「頭脳」が重要なんですね。
例えば、夏には様々なセミの鳴き声が聞こえてきますね。セミに対して無関心で、知識もない人にとっては、すべて同じ「セミの声」なわけです。一方、セミの知識が豊富な人であれば、鳴き声別にどのセミか、そしてその鳴き声から聞き取れることが何かを聞き分けることができます。セミの鳴き声1つをとっても、対象=現実から得られる情報の豊かさや表情がまったく変わってきます。すぐれた編集者には、そういう「聞き分け」をすることのできる力があります。これはなにもセミの鳴き声に限ったことでないのは当然のことです。埋もれたり見過ごされたりしている事実や才能を発見して、それを世界に示すことができれば、僕たちの生活はそれだけ豊かになることができます。よい編集者はよい現実をつくるうえで役立てるはずです。

チェン
ただ編集対象の形を変えるのではなく、一次情報をしっかり把握したうえで、ターゲットへわかりやすく伝えられる形にすることが、できる編集の1つの形なのですね。