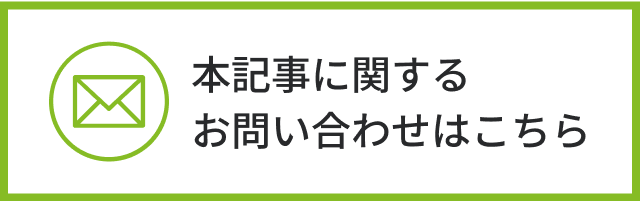M&Aの手順解説は第7回までとし、今回から4回にわたってM&Aを実施する際の重要な論点について紹介する。その1つに「買収価格」の検討・決定というプロセスがある。対象企業をいくらで買収するか、または買収金額として検討している価格が妥当であるかなどの検討プロセスのことである。ここでは、買収価格に関する意思決定の際に一般的に用いられるアプローチについて概説する。
※当記事は基礎からのM&A講座に掲載した内容を一部改訂して転載しています。
価格と価値
最初に、本稿で使用する「価格」と「価値」は以下の関係にあると考えている。
価格は対象物の値段や値札、価値は自身が対象物から得られる利益と想定する。仮に、A社が1億円で売りに出されていたら「価格」は1億円となる。自身がA社を買うことで得られるであろう利益が2億円で単純化のためそれ以外の要素を考慮しないのであれば、価格を上回る「価値」があるため、A社はお得な買い物となる。しかし、一方で、A社を買ったとしても0.5億円の利益しか得られないと考える人もいるであろう。この場合、価値は価格を下回っており、買い物は見送りになるであろう。すなわち、買い手にとって価値を超える価格では買えないことである。
価値は価格を判断するための材料ともいえる。「価格」と「価値」の大小関係の把握をすることが、買収価格検討の目的である。
事業価値と株式価値の関係
M&Aにおいては、何を買収するかにより買収価格が決まる。会社を買収するために買収対象会社の株式を取得するときには、買収価格は株式の価格を意味する。また、会社そのものではなく会社が保有する事業を買収するときには取得する事業の価格を意味することとなる。
株式の価格を検討するときには買収対象会社の「株式価値」の観点から買収価格を検討し、事業を買収するときには、買収対象事業の「事業価値」を検討することとなる。ただし、会社は事業から成り立っているため、株式を買収する際にも事業価値からの検討が先行して必要となる。
価値の概念
株式価値については、証券取引所などに上場している株式の株価が思い浮かぶだろう。上場企業の株価を発行済株式数で乗じたものも価値の1つであり、時価総額と呼ばれている。
しかし、上場企業を買収するときには、市場での株価が買収価格そのものとなるケースは少なく、時価総額より高い株価で買収価格が決まるケースが多くある。なぜか?一般的に上場株式市場は、株主の一部(「少数株主」または「マイノリティー」という)が株式を取引する場であり、会社そのものを買収する際には一定のプレミアムが株価に乗せられるからである。
プレミアムとは、一般的には支配権を獲得するために支払うものであり、株式市場での株価に上乗せされる。買収により企業そのものを「支配」できることに対する追加コストである。
少数株主として投資するときと、支配を目的として全株式を購入するときでは、会社に対する「支配」の度合いが異なるため、プレミアムの有無と同様に検討する買収価格の概念、すなわち買収対象の価値の概念も異なる。少数株主として投資する際の株式の価格はマイノリティーベースでの価値を、全株式すなわち会社そのものを買収する際にはマジョリティーベースでの価値を検討することとなる。
株式価値評価の必要性
M&Aを成立させるためには、最終的には売り手・買い手双方間で買収価格を合意しなければならない。
一般的に、買収価格は売り手にとっての価値と買い手にとっての価値の間で成立する場合が多いが、売り手の価格目線が高すぎる場合や買い手の価格目線が低すぎる場合、買収価格で合意することが困難になり、M&Aを成立させるのは難しくなる。逆に、売り手の価格目線が低すぎる場合や買い手の価格目線が高すぎる場合、売り手や買い手が得られるべき利益を放棄してしまうこととなる。特に買い手においては、買収後に問題を抱えてしまうこととなる(減損の可能性、必要な資金的手当て・投資が実施できないなど)。
従って、売り手と買い手双方が、対象会社の価値に合意するため、納得のいく手法にて株式価値評価を行う必要がある。
価値評価方法の概要
株式価値評価の手法について、あらゆる場面や当事者に汎用的に適用できる普遍的な理論は存在しない。一般的には、以下のアプローチからいくつかの評価手法を組み合わせて、複合的に株式価値を評価する場合が多い。なお、実務上価格の検討に際して比較的よく使われる評価方法は、マーケットアプローチの類似会社比較法とインカムアプローチのディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法(以下、DCF法)である。
なお、ベンチャー企業に対する評価につき、後述「ベンチャー企業評価」を参照されたい。
マーケットアプローチ
株式市場での株価をもって評価する方法、もしくは評価対象会社と事業内容などが類似している上場会社と業績・財務数値を比較することで、相対的に評価する方法(いわゆるマルチプル法)などがマーケットアプローチに分類される。
インカムアプローチ
買収対象会社の利益ないしはキャッシュ・フローに基づいて価値を算定する方法である。支配権を得ること、つまり、買収対象会社の利益やキャッシュ・フローなどを支配できるということが、このアプローチの考え方の基礎にある。いわゆるDCF法が代表的な評価方法である。
コストアプローチ
買収対象会社の貸借対照表の純資産から価値を評価する方法である。中小企業のM&Aで頻繁に用いられている手法であり、客観性を重視した評価手法であるが、将来価値が反映されないことから実際の株式価値から乖離する場合が多い。
類似会社比較法
マーケットアプローチに分類される類似会社比較法は、価値評価としては簡易に実施でき、非上場会社の価値の検討も可能であることから、買収価格の検討の初期的段階などで使用されることも多い。一方、業種・規模によっては、類似会社の選定が困難な場合があるため、類似会社を慎重に検討する必要がある。
類似会社比較法は、買収対象会社に事業内容等が類似した上場会社の時価総額・財務数値から対象会社の株価を類推する評価方法である。一般的には下記の手順図1により実施される。
出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
類似会社比較法では、「Ⅰ上場類似会社の選定」と「Ⅱ採用する倍率の選択(採用する財務指標)」が重要なポイントとなる。すなわち、類似会社が適切に選択できないと適切な倍率が算出できず、不適切な倍率から算出された株式価値はまた買収価格の検討としては、不適切だからである。
「Ⅱ採用する倍率の選択」とは、どの財務数値から算出された倍率を選択するのかを意味している。例えば、多額の設備投資を必要とし、減価償却費も多額である製造業などはEBITDA(税引前償却前営業利益)に基づく倍率が選択されることが多い。
「Ⅲ上場会社の倍率の算出」では、上場類似会社の時価総額に有利子負債を加算し、有価証券など(みなしの事業外資産とする。詳細後述)を減算した事業価値を算出し、上場類似会社のEBITDAなどの財務数値で除して倍率を求める。その後対象会社のEBITDAなどの財務数値を倍率に乗じて事業価値を求める。
事業価値から株式価値を算出するためには、事業価値に対象会社の有価証券などを加算、有利子負債などを減算する。上場類似会社の時価総額から事業価値を算出した手順の逆を辿ることで、類似会社と比較した際の対象会社の価値評価となる。
DCF法
インカムアプローチに分類されるDCF法は、買収対象会社の将来キャッシュ・フローに基づいて株式価値を評価する方法である。DCF法では、将来キャッシュ・フローを割引率で割り引く(ディスカウントする)こととなるため、評価に必要な要素は「キャッシュ・フロー」と「割引率」である。この2つの要素をもって、株式価値算出の基礎となる事業価値を最初に検討することとなる。一方、将来キャッシュ・フロー、すなわち事業計画に恣意性が入る可能性があるため、事業計画を慎重に検討する必要がある。
キャッシュ・フロー
DCF法で使用するキャッシュ・フローは、将来の見込みキャッシュ・フローである。そこで、キャッシュ・フローは、買収対象会社が作成した将来の事業計画から算出することとなる。通常、会計上の利益は実際のキャッシュの出入りを表すものではないので、事業計画の利益見込みに一定の調整を実施して将来の見込みキャッシュ・フローを算出する。一定の調整とは、キャッシュ・アウトを伴わない会計上の費用項目である減価償却費、費用項目ではないがキャッシュ・アウトを伴う設備投資および売掛金・買掛金などから発生する運転資本の将来の増減見込みなどを、事業計画年度ごとの利益見込み額に加減算することである。なお、この利益見込み額に一定の調整を施したキャッシュ・フローはフリー・キャッシュ・フロー(FCFと表記されることが多い)と呼ばれ、債権者および株主に帰属するキャッシュ・フローである。
割引率
割引率とは、上記のキャッシュ・フローを割り引く際に使用する値である。ここで「割り引く」とは、将来の見込みキャッシュ・フローを今時点の価値に換算することを意味する。
割引の基本概念
下の図2の現時点での年利回りは10%である。一方、来年得られる110円は、今の価値は100円である。
出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
買収の際に買収対象会社が作成した事業計画から算出されるキャッシュ・フローと割引率に置き換えると、以下のような関係が成り立つ。
買収を検討している事業が、来年に110円のキャッシュ・フローが得られるとする。割引率に10%以上の値を使用すると今の価値は100円以下と計算される。割引率に10%以下の値を使用すると今の価値は100円以上と計算される。この場合、5%の割引率を用いる状況にあれば、当事業は今時点の価値で100円以上の事業価値と計算されるため、この事業を100円で買収できれば割安で買収できたこととなる。
割引率の推計
将来見込まれるキャッシュ・フローを今時点の価値に変換するに当たり、買収対象事業の将来キャッシュ・フローに対するリスク(=リターン)を割引率に反映させることとなる。DCF法では、割引率として「加重平均資本コスト(Weighted Average Cost of Capitalのことであり、「WACC」と略される)」が用いられることが多い。ここで、加重平均されるコストとは、有利子負債コストと株主資本コストである。投資家(株主と債権者)に支払われるべきコストという観点から、「資本コスト」と呼ばれる。
WACCの構成要素は以下の図3の通りである。
出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
負債コストは、負債利子が税金の節減効果があることから、税引後の負債コストを用いる。
株主資本コストの推計は以下の図4の通りである。下記の式はCAPM(Capital Asset Pricing Model)と呼ばれている。
出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
リスクフリーレートは、指標とされている長期の日本国債の利回りが使用されることが多い。
エクイティリスクプレミアムは、株式市場のリターン率からリスクフリーレートを控除して算出される。株式市場のリターン率の計測期間は、一定程度長期間であることが望ましいといわれている。
βは、株価の変動性を表す値であり、買収対象会社に事業内容などが類似した上場会社の株価と株価指数(日本の株式市場におけるTOPIX)などの一定期間の相関性から算出される値である。複数の上場類似会社から算出されたβは、買収対象会社が属する業界の株価の変動性を表すこととなり、ひいては市場が見ている業界のリスク(変動性)を数値化したものといえる。
サイズリスクプレミアムは、買収対象会社の企業規模に応じたリスクのことである。企業規模が小さいと株式のリスクは増し、逆に大規模な企業は株式のリスクも相対的に低いことをその理由としている。CAPMでは補足しきれないリスクを補う値として、その加算の扱いは昨今の評価実務として定着しつつある。
負債コストと株主資本コストを加重平均することでWACCを推計することとなる。なお、有利子負債比率および株主資本比率は、買収対象会社の現在の構成比率ではなく、将来予想される構成比率を使用する方が整合的である。買収対象会社固有の構成比率という考え方もあるが、一般的には買収対象会社に事業内容などが類似する上場会社の資本構成を用いることが多い。
継続価値(Terminal Value)
キャッシュ・フローは買収対象会社の事業計画から算出される。しかし、事業計画は3~5年程度までしか策定されていないことが一般的である。そこで、事業計画期間以後のキャッシュ・フローをどのように推測するかが問題となる。
事業計画期間以降のキャッシュ・フローについては、事業計画最終年度のキャッシュ・フローが一定率で永久的に成長する仮定を置くことが一般的である。事業計画期間以降の成長は、"永久"であることを鑑み、買収対象会社が存在する国の長期のインフレ率予想などを参考に決定することが多い。継続価値の算出式は以下図5の通りとなる。
出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
事業価値から株式価値の算出
買収対象会社の将来FCFと割引率ならびに継続価値をもって計算される価値が「事業価値」である。事業価値は、将来FCFの現在価値合計の総和といえる。
出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
事業買収を検討しているのであれば、ここまでのプロセスで概ねの買収価格検討はできることとなる。全株式の取得、すなわち会社を買収する際には、事業価値から株式価値を算出する必要がある。
事業価値から株式価値を算出するには、事業価値に加算する「事業外資産」および減算する「有利子負債」の検討が必要となる。事業価値から株式価値を算出するためのイメージは図7の通りである。
出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
事業外資産
事業外資産とは、事業の用に供していない資産のことである。事業外とは、事業から創出されるFCFに反映されていない資産を指す。代表的な事業外資産として、事業を運営する上で売却することに制約の無い(投資)有価証券や、遊休の不動産などが挙げられる。また、現預金残高から事業運営上必要な運転資金を控除した余剰の現預金残高も事業外資産として取り扱われることが多い。事業外資産、事業内資産の区別は一概に判断できないことが多いため、買収対象会社の分析およびヒアリングなどが必要である。
有利子負債
買収対象会社が外部の資本家から調達した有利子負債の合計額を指す。銀行からの借入金や社債、リース債務などが代表例である。
ベンチャー企業評価
独自のアイデアや技術を基に、新しいマーケットに、新しいサービス、商品を展開するベンチャー企業に対する評価は、上記にて述べた評価手法とは異なる。理由としては、事業リスクが通常の企業より極端に大きく、事業計画中赤字の状況の可能性が高いため、通常のDCF法、マルチプル法では評価できないことが多いからである。
実務上ベンチャー企業はExit Multiple法で評価されることが多い。Exit Multiple法は、DCFのインカムアプローチをベースに、Exit Multipleによる継続価値を加え、分析される手法である。
また、ベンチャー企業評価における主要な論点は以下図8の4点が考えられる。
出所:デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
1 事業計画
ベンチャー企業の事業計画を分析するうえでは、技術開発、商業化といったマイルストーンの達成状況や資金調達のタイミングに特に注意を払う必要がある。売上高については、市場規模・成長率・実現可能性、費用については、使途・事業拡大に伴う費用の使途の変化、ファイナンスについては、キャッシュバーンの水準・過去のファンドレイズのバリュエーションなどをチェックする必要がある。
2 成長ステージと割引率
ベンチャー企業評価について、CAPMに基づく加重平均資本コスト(WACC)ではなく、実務上図9のベンチャーの各ステージにおけるリスクと期待収益を考慮した割引率を使用することが多い。
出所: Valuation of privately held company equity securities issued as compensation published by AICPA Venture Capital Rates of Return, Scherlis and Sahlmanよりデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社作成
3 継続価値
DCF法における継続価値について、事業計画期間以降、成長率が徐々に減少し、その後一定の永久成長率で成長すると仮定する前提(永久成長モデル)となるが、ベンチャー企業は一般に計画期間後も急成長が見込まれるため、継続価値の計算に永久成長モデルを適用することは難しく、通常はExit Multipleが用いられる。Exit Multipleはその名の通り、将来の時点で対象会社株式を他者に売却、あるいはIPOすること(Exit)を前提としている。対象会社株式の継続保有が予定されている場合でも、対象会社株式の事業計画最終年度の成長率が高いことから、上場類似企業を参考に仮に売却した場合のキャッシュ・フローをExit Multipleを基に計算することが多い。
Exit Multipleを計算するに当たっては、事業計画最終年度の高い成長率を反映した類似会社を設定できるかがポイントとなる。
4 資本構成と分析手法
ベンチャー企業は多様な資金調達手段を取っており、複数の種類株式を発行しているため、株式価値総額を計算後、各種類株式に当てはめる手続きが必要となる。
詳細は「ベンチャー企業の資本調達手段に対応した評価手法について」を参照されたい。
価値の理解と検討
買収価格を検討するに際しての事業価値および株式価値算出の概要は以上の通りである。複数の評価手法があるため、算出された価値は評価手法ごとに相違することがある。そこで、評価手法ごとに算出された価値の差異の理由を把握することが必要となる。
一般的に差異の原因として考えられるのは、例えば、DCF法が中長期的な利益を使用するのに対して、類似会社比較法では今期の利益などを使用することによるタイミングに起因する差異やDCF法の割引率と類似会社比較法の倍率値の水準の差異などである。評価手法が異なると算出された価値に差異が発生するケースは比較的多く発生する。従って、各手法の価値の差異、業界の特性を踏まえ、複合的に価値の検討が必要である。
また、DCF法については、使用する事業計画の内容により価値が大きく変動する。事業計画が強気か弱気か?などの観点から、売上高計画・利益計画の合理性・達成可能性・実現可能性等を検討することは、DCF法の重要なポイントである。対象会社が策定した事業計画をDCF法にそのまま使用して価値を算出することもあるが、事業計画の検討結果に応じて買収者が事業計画に修正を加えることもある。修正内容如何により対象会社の価値も異なるため、慎重な検討が必要である(事業計画に直接修正を加える方法以外にも、割引率にそのリスクを反映させる方法なども考えられる)。
おわりに
買収価格を検討するに際しての事業価値および株式価値の概要は以上の通りである。価値を検討するには、買収対象会社の事業計画に加え、多数の株式市場からの情報が必要である。価値評価の難しいところは、1つの変数の採用を誤ると、価値が大きく変わり得る可能性があるところである。また、近年ベンチャー企業への投資が増え、普通株式に加え、優先株式、ストックオプションなども発行されるケースが多く、ますます評価実務が複雑化の傾向である。
加えて、理論的に正しく計算できたとしても、想定していた買収予定価格と価値に乖離が生じることもある。この場合には、算出された事業価値・株式価値と買収予定価格との乖離理由・原因を分析し、その理由を明らかにする必要があると考える。
次稿第9回は、ストラクチャーについての論点を取り上げて論じる。