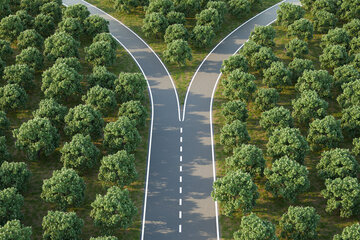日本のスポーツビジネスの転機とこれから
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
川端 一成

2016年、日本のスポーツビジネスは新たな時代を迎えました。内閣府が「日本再興計画」でスポーツを国の成長産業と明確に位置付けたことで、これまで“お金儲け”とは縁遠かったスポーツ業界に、ビジネスとしての積極的な発展の機運が生まれました。国の成長戦略の一翼を担うことで、業界のマインドも大きく転換し、新たな挑戦や投資が加速しています。今回はスポーツビジネスのスペシャリストで新しいeスポーツのビジネス化を推進しているデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーの里崎慎と小谷哲也に話を聞きました。(聞き手:編集部 川端)
目次
2013年に打ち出された日本再興計画では、当時の成長産業10分野の一つにスポーツビジネスが選ばれました。2012年時点で約5.5兆円とされていたスポーツビジネスの市場規模を、2025年には15兆円規模に――つまり約3倍に拡大させようという旗を国が掲げました。これは単なる数字の話だけではなく、スポーツが社会に与えるインパクトや、産業としての可能性を国が正式に認めたという意味合いが大きいです。
この国の方針決定が、スポーツ業界だけでなく企業や自治体、メディアにも大きな影響を与えました。オリンピックの招致、スポーツ庁の創設、各種スポーツリーグのプロ化促進など、スポーツを「社会を動かす力」として位置づける動きが加速しました。
スポーツビジネスの社会的価値の再発見
コロナ禍はスポーツビジネスに大きな打撃を与えました。しかし、里崎は「逆に“スポーツの本当の価値”を改めて考える大きなターニングポイントになったとも考えています。広告宣伝やイベント集客だけではなく、スポーツが持つ社会的価値やエンターテインメント性に、リーグやクラブといったコンテンツホルダーだけでなく、企業も、ファンも、真剣に向き合うようになった」と強調します。
SDGsやESGの観点からも、スポーツを支援する企業が増えています。従来は広告宣伝費の一部としてスポーツを活用していた企業も、今は“社会課題の解決”や“地域活性化”といった目的で、より本質的な関わり方を志向し始めています。
例えば、スポーツを通じた健康増進プログラムや、子どもたちの教育支援、障がい者スポーツの普及、地域コミュニティづくりなど、スポーツが担う役割はますます多様化しています。

日本と世界のスケールの違いと課題
日本のスポーツビジネスが拡大してきた一方で、海外との市場規模の差は依然として大きいのが現状です。例えばサッカーのプレミアリーグとJリーグの規模の差は歴然です。最大の違いは“ベッティング(賭け)”の存在。欧米ではスポーツベッティングが巨大な市場を形成しており、放映権料なども含めてお金の動く桁が違います。
日本では法規制のハードルが高く、スポーツベッティングが解禁されていません。そのため、スポーツコンテンツのマネタイズ手法が限られ、市場の成長に時間がかかっている面があります。実際、海外ではスポーツベッティング市場がスポーツビジネス全体の成長エンジンになっており、放映権料やスポンサーシップの規模にも直結しています。
さらに、海外ではスポーツが“エンターテインメントコンテンツ”として幅広い層に受け入れられており、メディアやテクノロジーの進化も市場拡大を後押ししています。日本でも今後、法制度や社会的理解が進めば、大きな成長余地があるといえます。

お金を出す企業と受け手の関係性が変わる
「企業からの投資も増えていますが、課題も残っています」と里崎。「今まではスポーツと縁のなかった企業も興味を持つようになりましたが、コンテンツホルダー側が企業の期待にこたえられる体制を整えなければ、せっかくのチャンスを逃してしまうことも多いです。」
「スポーツビジネスの成長には“お金を出す側”と“受け手”であるスポーツ団体やリーグ、選手たちの両輪がうまく回ることが大切です。広告宣伝だけでなく、ESGやSDGs、社会貢献、地域連携など、多様な切り口で価値連携できるかが問われています」とコメント。
今後の日本スポーツビジネスへの期待
スポーツビジネスはまだ「これから」のステージですが、社会的意義や持続可能性を重視した新しいモデルが生まれつつあります。高校野球やアマチュアスポーツにももっと資金が流れる仕組みづくりが必要ですし、ビジネス化が進めば選手や現場を支える人たちにもより良い環境が提供できるようになると考えられます。