企業価値向上、問われる「執行」と「対話」のバランス=M&Aフォーラムレポート

東京証券取引所がPBR(株価純資産倍率)低迷企業に改善を要請しているのに加え、昨今の円安で海外の機関投資家も経営層との連携強化を志向しており、上場会社にとって企業価値向上が喫緊の課題となっている。こうした中、デロイト トーマツ グループはこのほど、「M&A Executive Forum Japan 企業価値向上のためのポートフォリオ リバランス」を開催した。経営者、社外取締役、アクティビスト、アドバイザーを代弁する登壇者が基調講演やパネルディスカッションを行い、企業価値向上や持続的成長の実現策について討議した。
目次
本フォーラムは2025年3月4日、上場会社の経営幹部や金融機関など多様なステークホルダーが参加して都内のホテルで開かれた。主要なプログラムは次の3つであった。
1.【基調講演①】企業価値向上の要諦
CVCキャピタルパートナーズ日本法人 最高顧問藤森義明氏
2.【パネルディスカッション】異なる立場から考える企業価値向上の様々なアプローチ
複数の企業で社外取締役を務める浅野敏雄氏
米投資会社カナメ・キャピタルの槙野尚氏
デロイト トーマツ エクイティアドバイザリー合同会社(DTEA) 代表執行役社長古田温子
デロイト トーマツ グループ ボード 議長永山晴子
3.【基調講演②】ポートフォリオ リバランスの要諦
半導体材料企業レゾナック・ホールディングス 取締役染宮秀樹氏
本稿では、冒頭と閉幕でのあいさつの内容も含めて、このフォーラムで示された企業価値向上の方策について紹介したい。
PBR改善が求められる背景
冒頭あいさつでデロイト トーマツ グループ CEO(最高経営責任者)の木村研一は、日本の上場会社が企業価値向上を求められている背景について説明した。木村のプレゼンテーションによると、PBRが1倍割れしている企業は東証プライム市場の51%を占めている。一方で、昨今の円安や調達金利の低下を背景に、海外勢による日本企業の買収規模は2024年に前年比74.5%増の3.6兆円相当に達した。
また、東証プライム企業の平均PBRは現在1.2倍であるものの、2024年に実施されたTOB価格を織り込んだ平均PBRの1.6倍を目指すべきであり、「上場会社にとっては企業価値向上が喫緊の課題となっている」と指摘した。
「選択と集中」を図り、リスク恐れず変革を
基調講演①では、投資ファンドでのバリューアップや上場会社の経営に長年の経験を持つCVCキャピタルパートナーズの藤森氏が、企業価値向上には「選択と集中」や「環境変化と組織の変革」の2点が重要だと指摘した。
選択と集中については、投資先の製薬会社がバリュエーションの高い事業に積極的な集中を行ったことが企業価値を生んだ体験談を披露。さらに、配当、自己株買い、M&Aのうち、資本市場から最も評価されているのはM&Aである点を定量的に説明した。ただ、M&Aだけをやっていれば良いのではなく、大事なのは「リスクを恐れずに変革を起こす企業文化」であると力説。日本企業に限らず歴史の長い企業は安住を求めて、「コンフォートゾーン」に入りがちだと警告した。
3段階で企業価値向上を考える
パネルディスカッションでは、企業経営者、社外取締役の立場から浅野氏、バイサイドの機関投資家の目線からカナメ・キャピタルの槙野氏、アドバイザリーの立場からDTEAの古田が登壇し、資本市場を取り巻く多様な立場から、3つの段階を経る形で討議を行った。
① 企業価値向上へのコミットが強く求められる背景
まず、会社が企業価値向上へのコミットを強く求められるようになった背景として、外部からの注目度の高まりや、関わり方の変化があると指摘された。
旭化成の元社長で現在は複数の企業の社外取締役を務める浅野氏は経営者として、取引先の金融機関が主導する「バンクガバナンス」から資本市場による「エクイティガバナンス」への転換を実感していると指摘。多くの経営者は、リスクを恐れず変革に取り組んでいると思うが、市場からの評価は厳しい。「昔は、株式の持ち合いのもと、金融機関に事業説明すれば済んだ。しかし今は、企業価値向上策について、株主からコミットが強く求められ、対話が活発になっている」と語った。
古田も「企業価値向上への取り組み方が不十分であると理解された場合に、取締役会の刷新を迫るなど投資家からの手段がエスカレーションしてゆく」事例を紹介した。
槙野氏は、生え抜きが経営の主体だった日本企業においても「「アウトサイダーである社外取締役が存在感を増している。また、世論も企業価値を向上できない企業を厳しい目で見るようになった」と指摘。当該企業が同意に至っていない海外勢による買収提案についても「メディアも含めて反発ばかりではなく相当の理解を示すように変わっている」と、時代の変化ぶりを語った。
② それぞれの立場から重要と考える論点
企業価値向上に重要なのは「取締役会での執行と監督のバランス」と「資本市場との対話」の2つであるとの点で意見が一致した。しかし、方策に関しては、パネリストの立場ごとに見解が分かれた。
槙野氏は機関投資家の目線から、「株価と経営との結節点になるのが取締役会」とした上で、「取締役会が監督機能を果たしているかが重要。現状を変える自己否定的な部分がある以上、社外取締役が過半数を占める意義は大きい。せめて議長は社外取締役にすべきではないか」と主張した。さらに株価から資本市場のメッセージを読み解ける経営者が不可欠であるとし、「株主との対話は誰がリーダーとなるか、責任ある人を一人置かないといけない」と述べた。
一方、浅野氏は経営者の立場から「企業価値向上の要諦はまず執行面である。投資家との対話を重視しつつ経営会議でしっかり議論し本業で稼げなければいけない」と語り、「社外取締役が必ずしも過半数である必要はないのではないか。取締役会での反対意見は議事録に採録されるものであり、その発言(の内容)は非常に重い。むしろ昨今の不祥事対応、買収提案対応などの例では取締役会議長は、社外取締役のほうが有効であると思われる」と強調した。
古田は資本市場への「総合プロモーション資料」となる中期経営計画の重要性を指摘した。中計を見ればその企業が目標としている株価に向けて「追加的な施策や資本政策だけでなく、それを実行できる体制である」かどうかが読み取れるためだとしている。
③ 上場企業に求められているアクション
個々の企業に必要なアクションとして、古田は、自社の株価を上昇させる余地がどこにあるのかを、資本政策なども含めて「聖域なく考えるのが非常に重要」であると強調した。アクティビストが求めてくる株価対策に先回りする目的もあるとしている。
人的な面の重要性も示された。取締役会を機能させるうえで、良い社外取締役を選ぶこと。スキルマッピングにこだわるよりも、「企業価値向上に資する、能力が高く信頼できる人を見極めて社外取締役の質を高める」(浅野氏)のに加えて、「次世代経営層をしっかり巻き込む」(古田)ことが、経営計画の達成には不可欠との指摘があった。
また、槙野氏は「再編が進んでいない業界がまだまだあるため、機関投資家が投資すべき強い企業を見つけにくく、株価も安くなる構造的な課題がある」と指摘。「本当に強い会社が日本の中から出てきて欲しい」とした上で、経営者がPEファンドなどをパートナーとするMBOや再編を通じたダイナミズム」を主導するよう訴えた。
「当たり前のことを徹底的に」が要諦
レゾナックの染宮氏は基調講演のはじめに同社の髙橋秀仁社長の「戦略はコモディティ、差別化はエグゼキューション」との言葉を紹介した。同社は2023年に旧昭和電工と旧日立化成が統合して誕生した「伝統的な日本企業(JTC)」(染宮氏)であったが、統合後、バリュエーションの高いスペシャリティ・ケミカルズ事業に選択と集中を図り、資本市場との効果的な対話を経て化学銘柄から半導体材料銘柄に移行したという。事業再編が進んだことを認めた一部のアナリストが、コングロマリットディスカウント抜きの株価評価をしているケースもあると述べた。染宮氏はレゾナックが目標としてきた「当たり前のことを徹底的にやり切れる会社を作る」ことこそが、企業価値向上の要諦だと強調した。
染宮氏によると、同社最大の特徴は経営チームにあった。統合による発足時に執行役員を両社合わせて32名から外部出身者を含む14名に絞り込んだ。このチームが「役員合宿を通じて意見を言い合える関係を築き、迅速な意思決定が可能となった」ことが、変革の原動力になったという。
デロイト トーマツも企業価値向上を支援
フォーラムの閉会時にはデロイト トーマツのストラテジー・リスク・トランザクションリーダーの鹿山真吾があいさつ。国内企業を対象とした大規模なディールや、従来では考えにくかった事前通告のないTOBが起きるなど、M&A環境は世界的に見ても「非常にユニークな状況になっている」と指摘。その上でデロイト トーマツとしても「グループのグローバルな知見を活かして、企業のお役立ちを果たしたい」と語った。
<登壇者>
藤森義明 CVCキャピタルパートナーズ日本法人 最高顧問
1975年 4月 日商岩井株式会社(現 双日株式会社)入社
1986年10月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社入社
1997年10月 ゼネラル・ エレクトリック・カンパニー バイス・プレジデント兼GE Medical Systems Asia CEO
2001年 5月 ゼネラル・エレクトリック・カンパニー シニア・バイス・プレジデント 兼コーポレートCECメンバー 兼 GE Plastics CEO
2005年 2月 GE Money Asia CEO
2008年10月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 取締役会長 兼 社長 兼 CEO(代表取締役)
2011年8月 株式会社住生活グループ株式会社(現 株式会社LIXILグループ)取締役 代表執行役社長 兼 CEO
2012年6月 東京電力株式会社 社外取締役
2016年6月 株式会社LIXILグループ 相談役
2016年6月 武田薬品工業株式会社 社外取締役 (現任)
2016年7月 ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役(現任)
2018年8月 日本オラクル株式会社 取締役会長(現任)
2019年6月 株式会社東芝 社外取締役
2020年3月 株式会社資生堂 社外取締役
浅野敏雄氏

2014年旭化成の代表取締役社長に就任、2024年より特別顧問。また、昭和女子大学の理事、公益財団法人がん研究所の理事長、公益財団法人発明協会や一般社団法人企業研究会、全国防衛協会連合会の理事・副会長に加えて、上場企業を含む大手企業複数社の社外取締役を務める。
槙野尚 Kaname Capital, Head of Research

2012年東京大学法学部卒業後、モルガン・スタンレーMUFG証券にて株式調査を担当。14年からみさき投資にてエンゲージメント投資に携わった後、2022年に米コロンビア大学経営大学院を修了(MBA)。同年から現職。
日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)。論文「創業家持分が多い企業のガバナンス」(みずほ証券資本市場アップデート)など。
古田温子 デロイト トーマツ エクイティアドバイザリー合同会社(DTEA)代表執行役社長

大手証券会社、IR/SRコンサルティング会社の取締役、経営人材コンサルティング会社のパートナーを経て、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社に入社、デロイト トーマツ エクイティアドバイザリー合同会社の代表執行役社長に就任。デロイト トーマツ入社以前は敵対的買収防衛支援、プロキシーファイト対応、アクティビスト対応、中期経営計画策定支援、経営幹部育成、幹部社員アセスメント等のアドバイザリー業務に従事。
永山晴子 デロイト トーマツ グループ ボード議長

総合商社、小売業、グローバル製造業、旅行業、金融業など幅広い業種の日本基準およびIFRS基準の監査業務、連結財務諸表作成支援、IFRS導入支援業務等の業務に従事。また、企業会計基準委員会、日本公認会計士協会の各種委員を務め、会計基準の開発に携わる経験を有する。著書に『監査の現場からの声 -監査品質を高めるために- 』(共著:同文舘出版)、『監査の品質に関する研究』(共著:同文舘出版)がある。
2018年6月より有限責任監査法人トーマツ 経営企画本部長(2020年8月まで)
2020年8月よりデロイト トーマツ合同会社 評議員、有限責任監査法人トーマツ 評議員(2022年7月まで)
現職(2022年7月より)並びにデロイトアジアパシフィックBoard of Directorsメンバー、AP Risk Committee Chair(2024年6月より)を務める。
社会貢献活動として、30% Club Japan Vice Chair、赤い羽根福祉基金運営委員を務める。
染宮秀樹 レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 最高財務責任者(CFO)
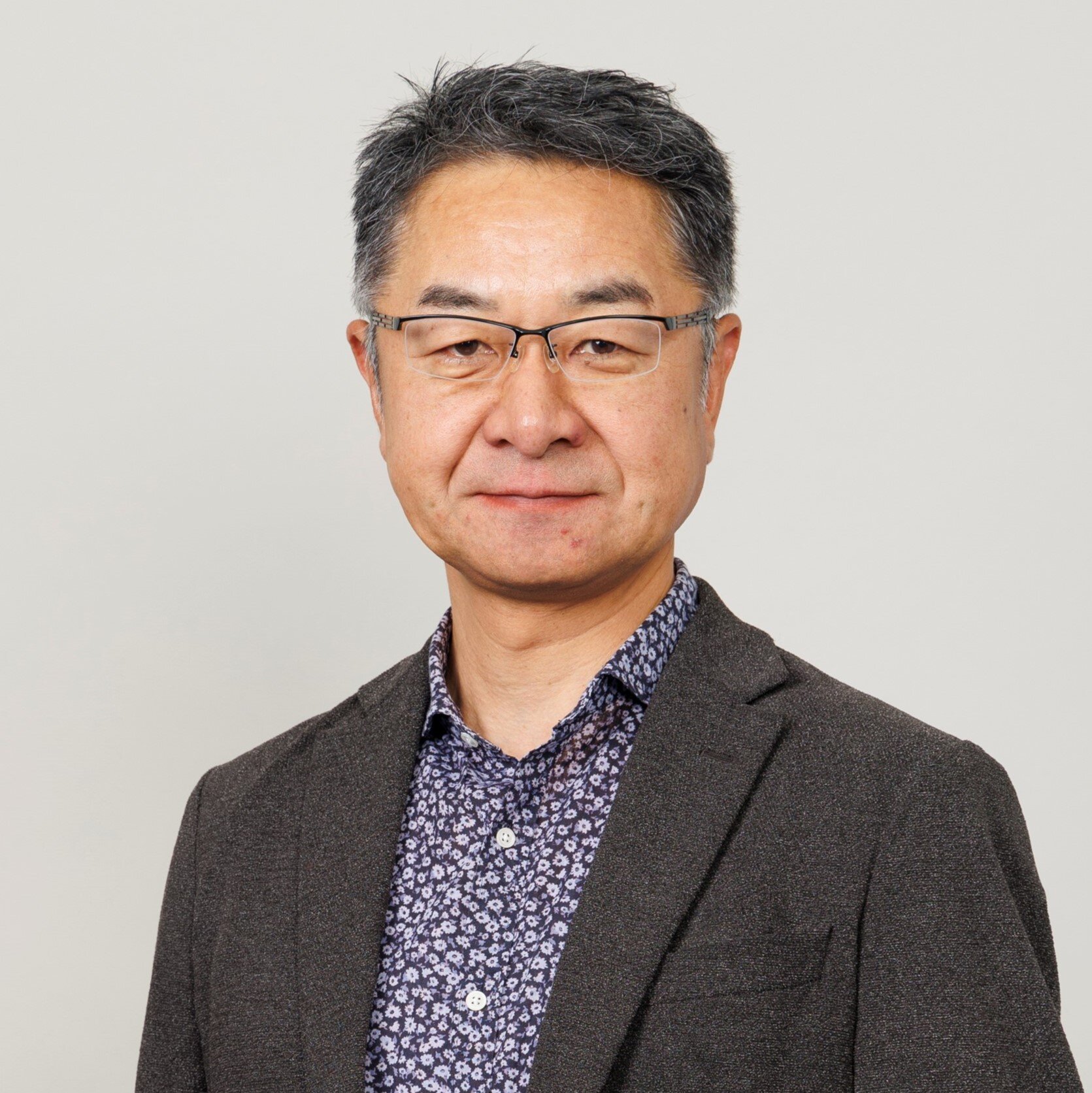
野村総合研究所を経てメリルリンチ日本証券、JPモルガン証券でテクノロジー・メディア・テレコム業界担当投資銀行業務の統括責任者を歴任後、ソニーに入社。同社では、グループ全体のM&A責任者、半導体事業のCFO、AIセンシングソリューション事業立ち上げに携わった。2021年10月昭和電工に入社、2022年取締役 常務執行役員 CFO。2023年1月より現職。
<関連サイト>



