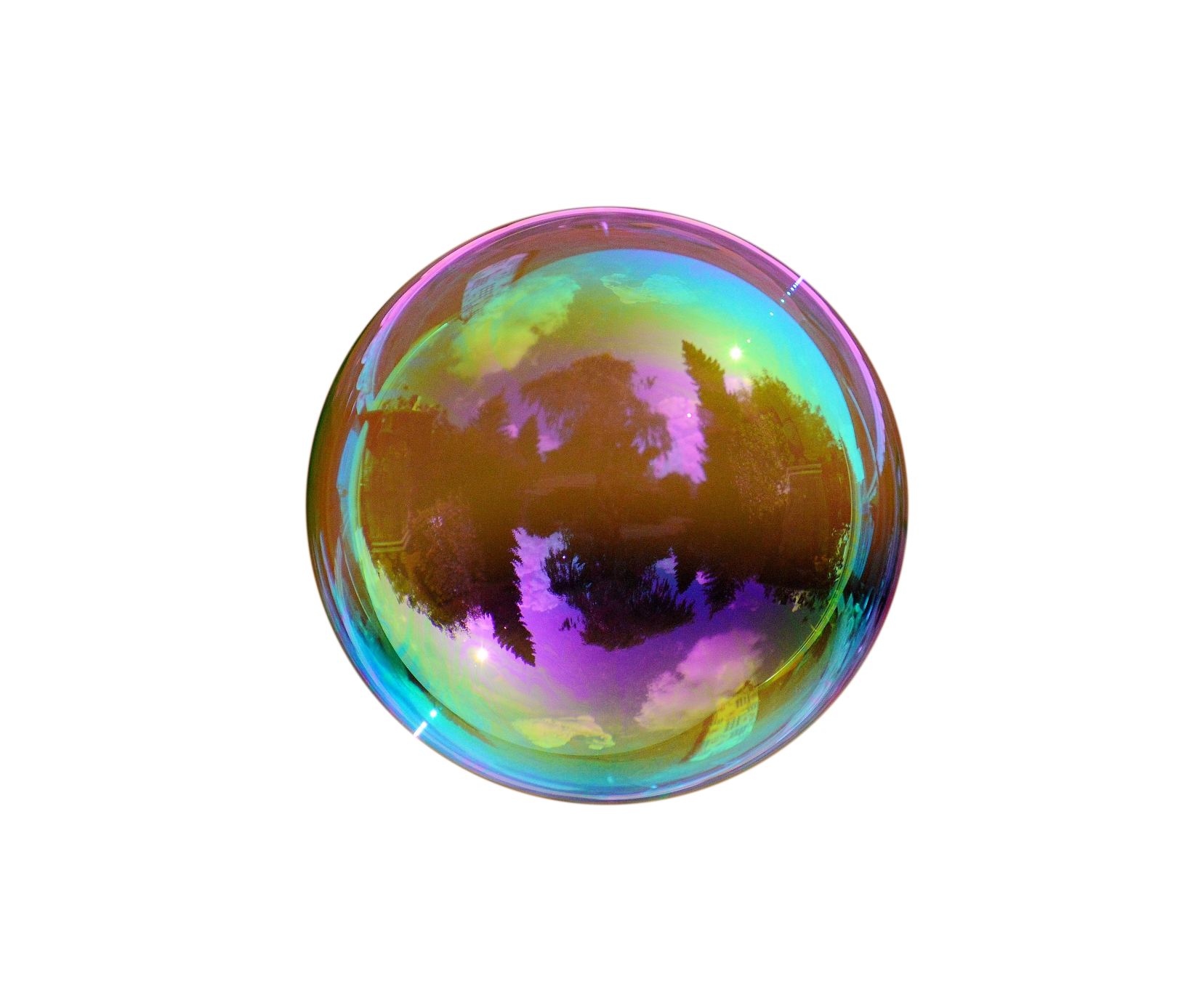
男女格差を評価するジェンダーギャップ指数で、日本は148ヵ国中118位、G7の中で最下位であるだけでなく、他のアジア主要国にも立ち遅れている。経済分野では、女性の役員や管理職の比率が低い。日本政府は「2025年に女性役員比率19%」など女性登用に関する数値目標を設定しているが、強制力がない努力目標のため、数字合わせに留まる企業もあり、男女格差の真の是正には不十分といわざるを得ない。女性が活躍する企業の方が業績が良いという調査結果が複数出ていることに加え、女性が活躍できない企業は投資家からの評価が下がり、人材獲得が難しくなるなどのリスクがあることも認識すべきであろう。実効性のある取り組みとして、少数派に一定の比率を割り当てる「クオータ制」の導入なども選択肢となり得るのではないか。
日本の男女格差は世界最低レベル
世界経済フォーラムは毎年ジェンダーギャップ指数を発表している。その2024年版で、日本は148ヵ国中118位と、G7の中で最下位であるだけでなく、アジアでも韓国の94位や中国の106位よりも下となっている。図1の通り、「教育」「健康」の値は高いが、「経済」「政治」の低さが顕著で、女性管理職比率、男女賃金格差、女性議員比率などが低水準であることが要因となっている。政治分野に女性が増えることで、経済分野での女性活躍推進に向けた政策が実現しやすくなる。両分野で女性が活躍できる環境が実現しない限り、国際的な立ち遅れを是正することは難しい。
図表1:ジェンダーギャップ指数
.png) データソース:World Economic Forum ”Global Gender Gap 2024”(※1)
データソース:World Economic Forum ”Global Gender Gap 2024”(※1)
政府の「女性版骨太の方針(女性活躍・男女共同参画の重点方針)2024」では、「2030年に指導的地位にある人々の性別に偏りがない社会を目指す」というコンセプトが掲げられている。もちろん男女半々があるべき姿であろうが、実態からすれば達成は困難である。政府は、経済、政治分野における女性比率を、意思決定に影響を与える分岐点となるクリティカル・マスの3割まで高めることを目指し、中間地点となる2025年の数値目標を設定している。詳細を図表2に示す。
上場企業は2023年3月期から女性管理職比率の情報開示を行っているが、政府は非上場企業を含む従業員101人以上の企業に対象を拡大して公表を義務化する方針を示している(※2)。
図表2:女性活躍に関する政府目標
.png)
「女性が活躍しない企業」が直面するリスク
女性の活躍が進む企業のほうが、ROE(株主資本利益率)、ROA(総資産経常利益率)、株式パフォーマンス、TFP(全要素生産性)など各種指標において、進んでいない企業よりも良い結果が出ているという調査結果が政府資料にも複数示されている(※4)。数値目標の設定に対しては「性別ではなく実力により評価すべきである」「女性を優遇することは男性差別になる」「無理に女性を登用すると人材の質が低下する」などの反論が絶えないが、戦略的に女性の登用を進めることは企業経営にとってメリットが大きい。ここではさらに踏み込んで、女性が活躍しない企業のリスクを指摘したい。
①資本市場における低評価
ある大手メーカーの2023年の株主総会で、CEO再任の賛成率が50.6%に留まったのは女性役員の不在が一因だったとされたことは、産業界に衝撃を与えた。また、内閣府が機関投資家などを対象に行った調査報告書によると、65.4%が女性活用情報を投資判断に活用しており、もっとも活用しているのは女性役員比率である(図表3)。女性が活躍できない企業は、資本市場で低い評価を受ける可能性がある。
図表3:ジェンダー投資の概要
.png)
データソース:内閣府 男女共同参画局「ジェンダー投資に関する調査研究報告書」(2024年4月)(※5)
②優秀な人材獲得が困難になる
女性管理職比率などが依然低水準にある企業は、若年層や優秀な人材から就職先として選ばれにくく、既に働いている女性人材の流出も起きかねない。少子高齢化が進み、あらゆる業種で人材不足が深刻化している日本企業にとっては深刻な問題であろう。
③グループ・シンク(集団浅慮)に陥り意思決定を誤る
グループ・シンクとは、判断能力が下がった集団が不合理な意思決定を行う状態を指す。同一性が高く閉鎖的な集団で起こりやすいとされる。一例として、内閣府の調査レポートでは、機関投資家の「ある会社が出した広告に、女性にとって望ましくない表現があったが、女性側から見たら違和感を覚えやすかったと思われる。世に出る前に早く気が付くことができたのではないか。意思決定や判断にまで多様性が浸透していることが重要」とのコメントが掲載されている(※6)。
④女性消費者に向けたイノベーションが生まれない
製品やテクノロジーの開発は男性の研究者・技術者を中心として行われていることが多いため、無意識の性差が日常的な製品にも反映されている。男性の人形を使った安全テストを経て開発された自動車のシートベルトは、妊婦などの女性が使っていて事故に遭った場合、重症化率が高いという問題が指摘された(※7)。女性がVR(仮想現実)酔いを起こしやすいのは、男性に合わせて開発されたHMD(ヘッドマウントディプレイ)の瞳孔間距離の不適合が主因であるとする研究結果もある(※8)。こういった問題を踏まえ、性差分析を取り込んで技術革新を行う「ジェンダード・イノベーション」を進める動きは世界的に進みつつある。
クオータ制のような制度導入も選択肢になりえる
投資家の評価を背景に女性役員の比率を高める動きは急速に進み、東証プライム上場企業では2024年7月に16.1%となっている(※9)。この比率を2025年に19%に引き上げるという政府目標は実現するかもしれない。ただし、企業によってばらつきがあることに加え、上場企業の女性役員のうち社外取締役と監査役の合計が占める割合は86%に達している。数字合わせによって女性比率を上げているだけで、社内女性の登用が進んでいない企業が多いことも否定できない。こうした点にも留意する必要がある。
また、デロイトが日本など10ヵ国を対象に行った調査によると、ジェンダー平等の先進企業で働く女性は、立ち遅れている企業に比べ、「所属組織へのロイヤリティ」「仕事でのモチベーション」「組織への帰属意識」「仕事への満足度」に加えて「仕事での生産性」に対しても大幅に満足度が高い(※10)。女性登用の本来の意義や、登用しないリスクを鑑みれば、意思決定層に占める女性の比率3割の早期達成を目指すべきである。
しかし、政府目標には強制力がないため、自主的な取り組みが進みにくい点が課題となっている。諸外国では政治・経済分野にペナルティを含めたクオータ制を導入する事例が多くみられる。図表4のように、罰金、上場廃止、企業の解散といった厳しい制度を設ける国もある。性別役割意識が比較的強いとされ、クオータ制導入に対して経済界の抵抗が強かったドイツも、女性比率低迷を背景に2015年に法律を制定した。
諸外国の取り組みは、企業の自助努力だけでは問題が解決しないことを示唆している。世界的に女性の登用が遅れている日本が迅速に成果を得るためには、政府目標を周知させ、実効性を高めることが必要である。それでも事態が改善しないならば、ペナルティを伴うクオータ制のような、一定の強制力を持つ制度の導入が選択肢になるのではないだろうか。
図表4:経済分野における諸外国のクオータ制とペナルティ
.png)
つながりによって女性活躍を支援する「Toget-HER」
2024年11月に、デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーは一般社団法人社外取締役女性ラボと共同で、「Toget-HER」プロジェクトを立ち上げた(※11)。本プロジェクトでは、企業や組織の垣根を超え、女性個人や女性支援団体などの横のつながり、役員・管理職女性と今後活躍する女性との縦のつながりの双方を通じて、女性の管理職・取締役の育成や輩出を支援する。政府や経済界への提言なども行い、女性が生き生きと活躍し意思決定に参画できる社会の実現に向け、働きかけていきたい。
構成=小林明子 DTFAインスティテュート 主任研究員
<参考文献>
※1 World Economic Forum ”Global Gender Gap 2024”
https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf
※2 厚生労働省 「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」(2024年8月)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/001285696.pdf
※3 内閣府 男女共同参画局 女性活躍・女性版骨太の方針 2024(男女共同参画の重点方針)(2024年6月)
https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/pdf/sokushin/jyuten2024_honbun.pdf
第5次男女共同参画基本計画~すべての女性が輝く令和の社会へ~(2023年12月一部変更閣議決定)
https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th-2/pdf/mokuhyo.pdf
「共同参画」2024年2月号
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2023/202402/202402_02.html
女性議員の国際比較(2023年9月)
https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/pdf/sankou2_23_09.pdf
厚生労働省「令和5年度雇用均等等基本調査」(2024年7月)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/71-r05/07.pdf
経団連「上場企業役員ジェンダー・バランスに関する 経団連会員企業調査結果」(2024年10月)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/069_kekka.pdf
※4 内閣府 男女共同参画局 女性の活躍状況の資本市場における「見える化」に関する検討会資料(2012年9月)
https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/mieruka/siryo/pdf/m01-03-3-3.pdf
経済産業省「ダイバーシティ2.0一歩先の競争戦略へ」(2017年4月)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/pdf/20170421/20170421_05.pdf
内閣府経済社会総合研究所『経済分析』第 201 号「情報開示の有無を考慮した女性活躍推進と企業業績の関係」(2021年)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/archive/bun/bun201/bun201a.pdf
※5 内閣府 男女共同参画局「ジェンダー投資に関する調査研究 報告書」(2023年4月)
https://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/pdf/r4gender_lens_investing_research_02.pdf
※6 内閣府「機関投資家が評価する企業の女性活躍推進と情報開示」
https://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/pdf/30esg_research_02.pdf
※7 「男女差47%」自動車事故で女性の重傷リスクが圧倒的に高い理由 キャロライン・クリアド=ペレス
https://president.jp/articles/-/45570
※8 Kay Stanney , Cali Fidopiastis, Linda Foster “Virtual Reality Is Sexist: But It Does Not Have to Be”
https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2020.00004/full
※9 上場企業役員ジェンダー・バランスに関する経団連会員企業調査結果(2024年10月)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/069_kekka.pdf
※10 デロイト トーマツ グループ「Women @ Work 2024: A Global Outlook」(2024年8月)
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/about-deloitte/group-diversity/jp-dei-women-at-work-2024-jp.pdf
※11 デロイト トーマツ、社外取締役女性ラボと女性役員や管理職のネットワーク構築、育成を目指す「Women Empowerment 『Toget-HER』 project」始動
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/news-releases/nr20240925.html


